旭川医科大学病院(北海道旭川市)が名医に推薦されている分野
専門医より推薦を受けた診療科目・診療領域
旭川医科大学病院は、複数の有名専門医(※)の間で「自分や家族がかかりたい」と推薦されています。
このページでは、専門医より推薦を受けた分野(科目、領域)の特色や症例数、所属している医師について取材・調査回答書より記載しています。
※推薦、選定して頂いた有名専門医の一覧表
- 消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
- 呼吸器センター(呼吸器内科)
- 呼吸器センター(呼吸器外科)
- 循環・呼吸・神経病態内科
- 腎臓内科
- 小児科
- 小児外科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 第3内科(血液・腫瘍内科)
- 膠原病内科
- 外科(乳腺内分泌外科)
- 放射線科
消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
分野 |
消化器・一般内科 |
|---|---|
特色 |
当科は、旭川医科大学が設立された折、第3内科として故並木正義教授が75年に創設され、94年に高後裕教授が第2代教授に就任し、現在に至っている。並木初代教授は、消化器病学、消化器内視鏡学の草分けとして多くの優れた臨床研究を生み出し、後任の高後教授の下では、消化器内科学と血液・腫瘍内科学を2本柱として診療および研究を行っている。大学病院においては、消化器内科と血液・腫瘍内科を担当し、同時に外来点滴センター(外来化学療法)、光学医療診療部のサポートを行っている。また、同門の奥村教授の主宰する総合診療部や鳥本教授がセンター長を務める腫瘍センターと連携して、総合内科や腫瘍内科を基盤とした高度先端医療および全人的医療を行う消化器・血液腫瘍制御内科の実践に力を入れている。なお、本院は、地域がん診療連携拠点病院および北海道高度がん診療中核病院の指定を受けている。 |
症例数 |
08年度の外来患者は25,000人、年間入院患者数延べ18,000人で、常時50人前後の入院患者がおり、平均在院日数は19日である ★消化管疾患=当科の内視鏡診療はほとんどが治療内視鏡もしくは特殊内視鏡であり、年間およそ5,000件行っている。最近は、ダブルバルーン小腸内視鏡やカプセル内視鏡による小腸病変(特に悪性リンパ腫や血管性病変など)の検査や、NBIやAFIといった光デジタル内視鏡を行っている。早期がんに対しては積極的にポリペクトミー、EMRやESDを行っており、09年度のがん内視鏡治療はおよそ200件であった。また、潰瘍性大腸炎、クローン病を中心とする炎症性腸疾患(IBD)の診療も精力的に行っており、拡大内視鏡観察を用いた疾患の再燃予測や、IBD合併がんの診断、ステロイド抵抗性の分子学的診断と、免疫抑制剤治療・抗TNFα抗体療法・白血球除去療法といった新しい治療を行っている。さらに、IBD患者で構成される患者会活動の支援など在宅医療支援も行い、年に1回、患者会との交歓会で医師と患者、家族との間で疾患や最新の治療法に関して理解を深め合っている ★肝疾患=C型慢性肝炎では、ペグインターフェロン+リバビリン併用療法を中心にして、個々の患者さんの病状に合わせた最適な治療を選択している。また、インターフェロン適応外や無効例では、抗酸化治療である瀉血療法と鉄制限食療法を積極的に取り入れている。肝がんでは、高分解能かつ低侵襲である造影超音波を早くから診断に用い、年間500例に達する。内科的治療では、従来からのPEIT(エタノール注入療法)、PAIT(酢酸注入療法)、TAE(肝動脈塞栓術)に加え、RFA(ラジオ波焼灼療法)も初期より導入している。また、外来化学療法チームと連携し、リザーバー肝動注化学療法も行っており、最近は分子標的治療(ソラフェニブ)症例も増加している。さらに、近年問題となっている非アルコール性脂肪性肝炎も、関連病院や糖尿病内科と連携を図り、症例を蓄積している。本院は肝疾患診療連携拠点病院であるため、当科はその中核としての役割を担っている ★胆膵疾患=胆膵疾患では、内視鏡や超音波を駆使した低侵襲な診断・治療として、総胆管結石に対する内視鏡的乳頭括約筋切開術や乳頭バルーン拡張術、胆管炎に対する緊急ドレナージ術、悪性胆道狭窄に対する内視鏡的胆管ステント留置術に加えて、正確な鑑別診断やがんの進展度診断のため胆管・膵管内超音波細径プローブや経口胆道鏡検査を行っている。08年度はEUS 300件、ERCP 150件、FNA 40件、PTBD・PTGBD 30件である。難治性である膵がん・胆道がんの治療においては、ゲムシタビンを中心とした併用療法による臨床試験を積極的に行っている。また、膵管内乳頭粘液性腫瘍や膵胆管合流異常、自己免疫性膵炎については、診断・治療方針に関する新たな知見を国内外に報告している ★血液腫瘍疾患=白血病、リンパ腫、骨髄腫などの血液腫瘍領域における各種抗がん化学療法や分子標的治療、造血幹細胞移植療法(自家・同種・臍帯血・ミニ移植)などを行っている。特に消化管悪性リンパ腫は消化管グループと共同で診療している。 |
医療設備 |
MDCT、MRI、超音波装置(造影対応)、内視鏡(上部、下部、小腸)、超音波内視鏡、光デジタル内視鏡、カプセル内視鏡、血管造影装置など。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 △
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 北海道」(ライフ企画 2010年6月)
- 消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
- 呼吸器センター(呼吸器内科)
- 呼吸器センター(呼吸器外科)
- 循環・呼吸・神経病態内科
- 腎臓内科
- 小児科
- 小児外科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 第3内科(血液・腫瘍内科)
- 膠原病内科
- 外科(乳腺内分泌外科)
- 放射線科
呼吸器センター(呼吸器内科)
分野 |
呼吸器内科 |
|---|---|
特色 |
呼吸器センターは臓器別診療科のさきがけとして08年5月に開設された。呼吸器内科と呼吸器外科、乳腺外科から構成されている。旭川医科大学病院は北海道での高次医療機関として機能することとともに、地域での総合病院としての役割も期待されているため、呼吸器センターではすべての呼吸器疾患に対応できる診療を行っている。特に、呼吸器系腫瘍、呼吸器感染症、気管支喘息については、大崎教授、豊嶋助教、睡眠時無呼吸症候群、呼吸不全については長内講師、小笠講師(学内)を中心に診療を行っている。竹内(中尾)医員はアスベスト検診外来を開設し、アスベスト関連呼吸器疾患のコンサルトを行っている。北田准教授は旭川医科大学病院での執刀数トップを誇り、安定した手術成績を挙げている。気管支鏡検査件数は年間約300例。手術件数は年間約400例で、肺がんは08年が70例程度。ともに、研修医が十分経験を積むことができる症例数と思われる。 |
症例数 |
08年度の呼吸器内科は年間外来患者数が8,449人、延べ入院患者数は6,092人で、症例の内訳は腫瘍(肺がん、縦隔腫瘍など)、呼吸器感染症(肺炎、胸膜炎、非結核性抗酸菌症など)、びまん性肺疾患(間質性肺炎・肺線維症、膠原病肺、過敏性肺炎、サルコイドーシスなど)、COPD(肺気腫、慢性気管支炎)など、呼吸器疾患で頻度の高い疾患を偏りなく診療している。また、肺高血圧症、肺血栓塞栓症などの肺循環系の疾患の診療実績も多い ★肺がんの診断と治療=早くから全国的な多施設共同研究に参加してきた。この経験に基づき、その時代のエビデンス(根拠)に基づいた最新の肺がん治療を行っている。片肺に限局する小細胞肺がんに対する放射線併用化学療法はもとより、局所に進行した非小細胞肺がんに対する放射線併用化学療法も多くの経験をもつ。さらに、進行した肺がんに対しては、臨床試験で良好な成績を挙げた新薬を積極的に導入して治療成績の向上を目指している。EGFR遺伝子異常の検索などの遺伝子診断もすでに導入している。気管支鏡検査技術の向上にも力を注ぎ、超音波気管支鏡下リンパ節生検(EBUS-TBNA)、超音波気管支鏡下肺生検(EBUS-GS)、バーチャル気管支鏡(Bf-NAVI)、蛍光気管支鏡(AFI/NBI)も導入している。増加する気管支鏡検査件数にあわせて気管支鏡の保有本数を増やし、待ち時間の少ない、清潔な検査を心がけている ★レーザー治療と蛍光気管支鏡=旭川医科大学は北海道で唯一のphotodynamic therapy(PDT:内視鏡的レーザー治療)を行う施設である。PDT用のレーザー装置はエキシマダイレーザーとPDレーザーを保有している。PDT症例の診断と経過観察のために、独自の蛍光気管支鏡システムであるPDS-2000を開発して使用している。現在は、小型軽量で新たな機能を搭載した次世代機を開発しており、完成が待たれる。気管支鏡を用いた気管支インターベンションも経験を蓄積しつつあり、アルゴン凝固法(APC)、ステント留置なども行う ★気管支喘息=高次機能病院という性格上、難治性の気管支喘息患者が多く外来通院している。ステロイド抵抗性の喘息患者も多く、希望する患者には抗IgE抗体による治療を行っている ★呼吸器外科と乳腺外科=08年の実績は、呼吸器外科127例(原発性肺がん64例、悪性胸膜中皮腫1例、転移性肺腫瘍15例、良性、気胸、膿胸、胸壁21例、縦隔腫瘍8例、その他18例)、乳腺・内分泌外科224例、内訳は、原発性乳がん165例うち乳房温存手術137例(83%)、乳房再建術5例、良性乳腺腫瘍24例、腋窩郭清、LN生検等27例、甲状腺3例であった。消化器一般外科58例。 |
医療設備 |
X線(単純、透視)、CT、PETCT、MRI、核医学検査、気管支鏡(EBUS-TBNA、EBUS-GS、Bf-NAVI、AFI/NBI、PDS-2000)、エキシマダイレーザー、PDレーザー、胸腔鏡、呼吸機能検査、放射線治療装置など。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 △
- 主治医指名 ×
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 北海道」(ライフ企画 2010年6月)
- 消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
- 呼吸器センター(呼吸器内科)
- 呼吸器センター(呼吸器外科)
- 循環・呼吸・神経病態内科
- 腎臓内科
- 小児科
- 小児外科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 第3内科(血液・腫瘍内科)
- 膠原病内科
- 外科(乳腺内分泌外科)
- 放射線科
呼吸器センター(呼吸器外科)
分野 |
呼吸器外科 |
|---|---|
特色 |
新設された呼吸器センター(大崎能伸呼吸器内科教授)の外科部門として診療している。対象症例は、腫瘍性疾患(原発性肺がんを中心とした転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、悪性胸膜中皮腫などの悪性腫瘍や良性腫瘍)および自然気胸、巨大肺嚢胞などの嚢胞性疾患や感染疾患など、呼吸器外科全般である。手術は胸腔鏡下手術から、気管支形成術や血管形成術を駆使した肺機能温存手術に努めるとともに、疾患の状況に応じて、胸壁や大静脈等の他臓器合併切除術などの拡大手術も施行している。 |
症例数 |
08年の年間呼吸器外科手術症例数は127例であり、原発性肺がん64例、転移性肺腫瘍15例、悪性胸膜中皮腫1例、縦隔腫瘍8例、良性腫瘍、気胸、膿胸、胸壁21例、縦隔腫瘍8例、その他18例であった。全手術の80%以上で胸腔鏡を利用した手術を施行している ★治療成績は、過去5年間の手術関連死亡例は2例(0.36%)、肺がんの切除成績はIA期78%、IB期65%、IIA期67%、IIB期45%、IIIA期36%である ★近年増加が予想される悪性胸膜中皮腫は未だ予後不良であり、標準治療が確立されていない。本施設でも、アスベスト外来の設置、局所麻酔下胸膜生検による早期発見に努力しているとともに、術前治療も念頭に置いた胸膜肺摘除術を含む集学的治療を積極的に施行している。 |
医療設備 |
X線(単純、透視)、CT、PET-CT、MRI、核医学検査、気管支鏡(EBUS-TBNA、EBUS-GS、Bf-NAVI、AFI/NBI、PDS-2000)、エキシマダイレーザー、PDレーザー、胸腔鏡、呼吸機能検査、放射線治療装置など。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 北海道」(ライフ企画 2010年6月)
- 消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
- 呼吸器センター(呼吸器内科)
- 呼吸器センター(呼吸器外科)
- 循環・呼吸・神経病態内科
- 腎臓内科
- 小児科
- 小児外科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 第3内科(血液・腫瘍内科)
- 膠原病内科
- 外科(乳腺内分泌外科)
- 放射線科
循環・呼吸・神経病態内科
分野 |
循環器科 |
|---|---|
特色 |
旭川医科大学病院は病床数602床、1日平均外来患者数約1,400人であり、循環・呼吸・神経病態内科学の病床数は47、年間入院患者数840人、1日平均外来患者数は170人である。狭心症、急性心筋梗塞、心不全、高血圧、不整脈、心筋症、心筋炎、弁膜症などの循環器全般の診療とともに呼吸器内科、腎臓内科、神経内科と連携して睡眠時無呼吸、肺高血圧、透析患者の心合併症、脳卒中の治療等にも携わり、肺循環、腎循環、脳循環領域にまたがる幅広い診断、治療を行っている。また、09年10月7日より道北ドクターヘリが就航し、基地病院である旭川赤十字病院への協力病院として上川、留萌、宗谷の道北3地方(利尻、礼文、焼尻島を含む)と空知地方北部、網走地方の遠軽、紋別地域をカバーして救急医療体制の充実化を図っている。 |
症例数 |
検査室で施行される心電図数は年間14,500件(概数、以下同)、運動負荷心電図100件、心臓超音波2,800件(経食道エコー70件)、ホルター心電図1,300件である。画像検査では、心臓核医学検査700件、冠動脈CT 80件、大血管CT 780件、心臓MRI 140件、血管MRI 60件であり、生理検査、画像検査ともに年々件数が増加している。また、09年度よりPET検査が可能となった ★心不全は長谷部教授の専門分野であり、超音波、心筋シンチ、心MRI、心臓カテーテル検査、心筋生検による質的診断とともにガイドラインに基づいた薬物療法、重症例には補助循環装置(大動脈内バルーンパンピング、PCPS、CHDF)や、心室再同期療法による治療を行っている。川辺特任准教授、竹原特任講師率いる心血管再生医療講座では、京都府立医大との共同研究でヒト心臓幹細胞移植臨床試験を厚生労働省の認可の下、今後開始予定である。その他、呼吸器内科と連携して心不全に対するCPAP、NPPV、ASVによる治療や、肺血栓塞栓症、肺高血圧症の治療も積極的に行っている ★高血圧も長谷部教授の専門分野であり、ガイドラインに準拠した生活指導、薬物療法とともに治療抵抗性高血圧、2次性高血圧に対する精査、加療を行っている ★虚血性心疾患の検査・治療では、経験の豊富な専門医(責任者:竹内講師)が24時間待機し、安定狭心症、不安定狭心症、心筋梗塞の治療にあたっている。08年度の緊急冠動脈造影検査数(インターベンション例を除く)は280件、カテーテルインターベンション治療は120件(バルーン拡張術のみ10件、ステント留置術110件)であり、良好な治療成績をあげている。また腎動脈や末梢血管に対する拡張術も行っている。その他、カテーテルによる侵襲的な検査、治療として心筋生検や経皮的僧帽弁交連裂開術も施行している。劇症型心筋炎に対する補助循環装置による治療も救急部と連携して行っている ★不整脈の診断・治療では、道北地方で唯一カテーテルアブレーションを行っている施設として、道北全域から紹介される患者さんを中心に診断・治療を行っている(責任者:川村保健管理センター教授)。08年度の心臓電気性理学的検査(アブレーション例を除く)20件、経皮的カテーテル電気焼灼術63件、ペースメーカー移植術:新規・交換合わせて30件、植え込み型除細動器移植術:新規・交換合わせて12件、心室再同期療法5件であり、心房細動に対するカテーテルアブレーション(肺静脈隔離術)も開始している。カテーテルアブレーションにはカルトシステムやエンサイトシステムといった、最新のマッピングシステムを導入し高い成功率を収めている。また、失神の原因精査のために紹介される患者さんも多く、神経内科グループと協力して、不整脈の検査とともにヘッドアップティルト試験、脳波検査などによる鑑別診断と治療を行っている。 |
医療設備 |
ICU 6床、心臓超音波装置3台、トレッドミル、エルゴメーター、ホルター心電計10台、CT、マルチスライスCT、MRI、心臓カテーテル装置、心筋シンチグラフィ、PET、大動脈内バルーンパンピング装置、PCPS(経皮的人工心肺補助装置)、CHDFなどを完備している。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 北海道」(ライフ企画 2010年6月)
- 消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
- 呼吸器センター(呼吸器内科)
- 呼吸器センター(呼吸器外科)
- 循環・呼吸・神経病態内科
- 腎臓内科
- 小児科
- 小児外科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 第3内科(血液・腫瘍内科)
- 膠原病内科
- 外科(乳腺内分泌外科)
- 放射線科
腎臓内科
分野 |
腎臓内科 |
|---|---|
特色 |
IgA腎症などの慢性糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、腎硬化症など、特に保存期の患者の治療に重点をおいている。膠原病に伴う腎障害および糖尿病性腎症に関しては、膠原病内科および糖尿病内科と協力し、診断および治療を行っている。当科では二次性高血圧として重要な腎実質性高血圧、腎血管性高血圧、内分泌性高血圧(原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫)の診断、治療を行っている。また睡眠時無呼吸症候群も二次性高血圧の原因として挙げられ、心・血管イベントのリスクになることが知られており、呼吸器分野と協力して睡眠時呼吸障害検査、持続陽圧呼吸療法の導入も積極的に行っている。虚血性心疾患を合併する透析患者には、循環器分野と協力して積極的にインターベンション治療を行っている。 |
症例数 |
★外来患者数・月間約1,300人 ★病床44床(循環器・呼吸器分野と共通床) ★腎生検(年間約30例)=IgA腎症は最も頻度の高い原発性糸球体腎炎とされており、臨床所見や腎生検による病理組織像より症例ごとに病期に応じた治療方針を選択している ★副腎静脈サンプリング(年間約15例) ★扁桃摘出+ステロイドパルス療法(年間約20例)=耳鼻咽喉科(頭頸部外科)と協力して、扁桃摘出+ステロイドパルス療法を行い、IgA腎症の根治治療を目指している ★透析患者のPCI=年間約20例に行っている。管理栄養士による腎臓病への専門的指導も行っている。透析治療はICU、CCU、病棟で実施している。 |
医療設備 |
ICU・CCU、血管撮影室、超音波診断装置、腎シンチグラフィ、血液浄化装置。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 北海道」(ライフ企画 2010年6月)
- 消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
- 呼吸器センター(呼吸器内科)
- 呼吸器センター(呼吸器外科)
- 循環・呼吸・神経病態内科
- 腎臓内科
- 小児科
- 小児外科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 第3内科(血液・腫瘍内科)
- 膠原病内科
- 外科(乳腺内分泌外科)
- 放射線科
小児科
分野 |
小児医療 |
|---|---|
特色 |
藤枝教授の主宰のもと、大学における診療・教育・研究活動の実践とともに、旭川市周辺と道北・道東という広大な医療圏の小児医療の維持と、その中心として活動している。大学病院4階フロアに小児関係の病室を集約し、東病棟には周産母子センター(NICU)、西病棟にはクラス最高の無菌室4床およびPediatric Intensive Care Unit(PICU)3床を配置し、小児外科病棟とともにあらゆる小児疾患に対応できる小児総合診療センター(病院内小児病院)を形成し、高度先進医療提供体制を作りあげている。診療・研究グループは内分泌/糖尿病/腎臓・神経/精神・循環器・血液腫瘍・新生児・感染/免疫の6つで、あらゆる小児疾患に対応できる体制をとっている。また、時代が求めている診療分野の一つである発達障害診療に対応するために、外来部門として子どもの発達診療センターを開設している。その他、開学以来、旭川厚生病院での新生児医療、道立旭川肢体不自由児総合療育センターでの発達障害児療育、北海道療育園での心身障害児療育と大学が密接なネットワークを形成し、厚みのある医療を実践している。研究においては、各診療・研究グループが独自の研究テーマを持ち研究を行っている。小児医療の最終目標は、疾患や診療グループにとらわれることなく、病気に悩む子どもとその家族の環境にも配慮し、子どもの成長と発達を視野に入れた全人的な医療を行うことが必須であり、我々はそれを実践している。 |
症例数 |
入院病床は小児科30床、NICU 6床(9床に増床予定)、GCU 6床(12床に増床予定) ★内分泌・糖尿病・腎臓=藤枝教授を中心に5人体制で低身長、性分化異常症、思春期発来異常、副腎疾患、甲状腺疾患、糖尿病、肥満などの各種内分泌疾患や遺伝性疾患の診療を行っている。また、新生児マススクリーニング:内分泌疾患の北海道におけるセンターとしても機能している。腎疾患では先天性腎尿路奇形、腎炎、ネフローゼ症候群、腎不全など小児腎臓病全般の診療にあたっている ★循環器=梶野准教授をチーフとした4人体制。道北道東地区の小児循環器疾患のセンター病院として機能している。年間の循環器入院患者数は小児科病棟に約140人、周産母子センターに約20人。心臓カテーテル検査は約70~100件、カテーテルインターベンションは約10~20件。産科との協力で胎児心エコー検査も外来で施行している ★血液・腫瘍=吉田講師をチーフとして4人体制。年間の新患入院数は25人前後、延べ入院数は170人くらいで病棟に常に15~20人の患者さんが入院されている。JACLS(小児白血病研究会)、JPLSG(日本小児白血病リンパ腫研究グループ)に属し、常に最先端の治療を心がけている。北海道で札幌を除いて唯一の小児移植センターとして同地区の小児血液腫瘍診療の要となっている ★新生児=林講師を中心に4人体制で診療。07年の新生児入院数は271件、人工呼吸管理数は47件。道北道東地区で唯一新生児外科疾患を診療でき、膜型人工肺などの高度先進医療を必要とする新生児疾患にも対応している。またUNICEF/WHOから「赤ちゃんにやさしい病院」に認定されており、母子関係への支援にも心がけている ★神経・精神=高橋講師を中心に4人の医師と臨床心理士1人で診療。てんかん、脳性麻痺、変性疾患、筋疾患などの診療に加え、子どもの発達診療センターでは荒木講師を中心に発達障害や不登校などの診療にあたっている ★感染・免疫=古谷野講師を中心に2人体制で診療。感染性疾患や自己免疫疾患、アレルギー疾患、消化器疾患まで幅広く診療している。予防接種外来を担当し、地域の予防医学に貢献すると共に、各地方自治体からの相談も受けている。 |
医療設備 |
CT、MRI、DEXA、SPECT、PET、US、血管カテーテル等、先進設備を完備。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ×
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 北海道」(ライフ企画 2010年6月)
- 消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
- 呼吸器センター(呼吸器内科)
- 呼吸器センター(呼吸器外科)
- 循環・呼吸・神経病態内科
- 腎臓内科
- 小児科
- 小児外科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 第3内科(血液・腫瘍内科)
- 膠原病内科
- 外科(乳腺内分泌外科)
- 放射線科
小児外科
分野 |
小児外科 |
|---|---|
特色 |
札幌以北では唯一の小児外科施設のため、北海道の北半分、半径約250kmの広い範囲の診療圏から患者さんを受け入れている。母胎搬送も含めた新生児外科症例や、多発障害症例のように多くの診療科が協働する症例に対しての集中治療、鏡視下手術が当科の特徴といえる。 |
症例数 |
当科が対象としている症例は、先天異常を扱う新生児外科、小児腫瘍外科、障害児外科、小児外傷外科である。扱う臓器は、頸部、縦隔、肺、胸壁、消化管、肝胆膵脾、後腹膜臓器と多岐に及び、年間150~200例の手術を行っている。08年の手術症例数は199例で、内訳は鼠径ヘルニア53例、内視鏡手術32例(噴門形成術16例)、喉頭気管分離19例、新生児外科18例、腫瘍11例、その他66例となっている。特に、内視鏡手術は全国に先駆けて取り組んでおり、ヒルシュスプルング病の鏡視下手術では本学で開発した新術式が全国各地で追試されている。さらに重度心身障害児の鏡視下噴門形成術は150例を超え、全国有数の症例数・成績となっている。また、新生児外科症例数は近年変化がないが、担当地域の出生数がここ10年で1/3に減少していることを考えると、従来専門医のいない各地で治療されていた症例が、当科へ集中してきているためと考えられる。 |
医療設備 |
NICU、クリーンルーム、MRI、CT、超音波、RI、PET、胸・腹腔鏡手術機器、内視鏡、24時間pHモニター、HFOなどを備えている。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 北海道」(ライフ企画 2010年6月)
- 消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
- 呼吸器センター(呼吸器内科)
- 呼吸器センター(呼吸器外科)
- 循環・呼吸・神経病態内科
- 腎臓内科
- 小児科
- 小児外科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 第3内科(血液・腫瘍内科)
- 膠原病内科
- 外科(乳腺内分泌外科)
- 放射線科
眼科
分野 |
眼科 |
|---|---|
特色 |
あらゆる難治性眼疾患に対し、それぞれに高度な専門知識を備えたスタッフによる診断および治療が一貫して行える診療体制を整えている。北海道の中核的病院の役割を果たしており、全道38施設を数える関連病院を始め、他施設や北海道外からの紹介患者が多い。 |
症例数 |
08年度の初診患者数は2,653人、再診患者延べ数は34,985人、手術件数は1,275件である ★網膜硝子体疾患に対しては、硝子体手術を年間500例以上行っている。網膜剥離には、強膜内陥術、硝子体手術にて重症例にも迅速に対応している。黄斑円孔、黄斑前膜に対しても、最新のスペクトラルドメイン光干渉断層計を備え、詳細で適切な診断・評価のもと、硝子体手術にて対応している。特に糖尿病網膜症に関しては、吉田学長の専門であり、全国有数の症例数がある。通常の諸検査のみならず、我が国では当施設にしかない眼循環を測定する種々の装置を完備し、さらに専門医による網膜光凝固、硝子体手術を行っている ★角膜外来では、すべての角膜疾患に対応でき、角膜ヘルペスを始め各種角膜炎などに対する診療治療、円錐角膜に対するコンタクトレンズ処方、近視、乱視に対するレーシックも行っている。特に角膜移植はNPO旭川医大アイバンクを発足させ、アメリカのアイバンクとも連携し、年間60件以上行っている。難治例には羊膜移植や人工角膜手術、ドライアイに関しては涙点プラグ、血清点眼治療なども行っている ★角膜、網膜の再生医療を目的に「眼組織再生医学講座」を立ち上げ、すでに培養角膜移植をなどの臨床医療に応用を始めており、難治性角膜疾患で成果をあげている ★遠隔医療支援システムを道内の関連施設およびシンガポール、タイなどのアジア諸国とつなぎ、リアルタイムで高度な医療が受けられるようにネットワーク医療支援を行っている。この功績により、吉田学長は09年度「情報通信月間」総務大臣表彰(個人賞)を受賞した ★白内障手術は年間約800件で、安定した術後成績を得ている ★緑内障は、各種薬物治療、レーザー治療、各種手術治療を緑内障専門医が行っている。最新の自動視野計を駆使して早期診断、経過観察を行い、疾患の進行防止に努めている。緑内障は個々の患者の背景に十分気を配り、病状を説明し、個別に適切なアドバイスを行うことが非常に重要と考えている ★ぶどう膜外来では、積極的に原因検索を試み、三大ぶどう膜炎とされるサルコイドーシス、ベーチェット病、原田病を始めとする各種ぶどう膜疾患の診断、治療を行っている ★斜視弱視外来では、視力の向上、眼位の矯正および両眼視機能の獲得を目的とし、専門医師と12人の視能訓練士が連携して、弱視に対して屈折矯正、遮蔽治療を、また小児の斜視や成人の麻痺性斜視に対して、手術とあわせて視能訓練も積極的に行っている。 |
医療設備 |
スペクトラルドメイン光干渉断層計(前眼部OCT・後眼部OCT)、角膜形状解析装置、超音波解析装置、レーザースキャニング検眼鏡(SLO)、各種自動視野計、種々の網膜脈絡膜循環測定装置、多局所網膜電図(VERIS)、蛍光眼底造影カメラ(HRA)、白内障手術装置インフィニティー、硝子体手術装置アキュラス、マルチカラー・ヤグレーザー凝固装置など。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 ○
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 北海道」(ライフ企画 2010年6月)
- 消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
- 呼吸器センター(呼吸器内科)
- 呼吸器センター(呼吸器外科)
- 循環・呼吸・神経病態内科
- 腎臓内科
- 小児科
- 小児外科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 第3内科(血液・腫瘍内科)
- 膠原病内科
- 外科(乳腺内分泌外科)
- 放射線科
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
分野 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 |
|---|---|
特色 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の疾患全般に対応している。特に失聴者に対する人工内耳手術や、慢性中耳炎・真珠腫性中耳炎に対する鼓室形成手術は症例数も多く、良好な術後成績を得ている。頭頸部がんに対しては、発声や嚥下などの機能を温存しつつ根治的な治療を目指して、放射線科と協力して集学的治療を行っている。確定診断に苦慮し予後不良となることが多い鼻性NK/T細胞リンパ腫の基礎的・臨床的研究を先駆的に行っている。また掌蹠膿疱症やIgA腎症などの扁桃病巣疾患の診断・治療および研究にも重点をおいている。最近では、中耳・副鼻腔手術におけるナビゲーションシステムや、内視鏡補助下甲状腺手術などの最先端技術も導入して治療を行っている。睡眠時無呼吸症候群に対しては、耳鼻咽喉科を含む複数科で構成された「睡眠クリニック」にて集学的な治療を行っている。日本耳鼻咽喉科学会認定専門医研修施設、頭頸部がん専門医制度研修施設。 |
症例数 |
09年1月~12月の外来患者数は20,947人、手術件数は520件である。主な内訳は耳科手術70例、がんを除く鼻副鼻腔疾患手術75例、口蓋扁桃摘出術69例、声帯ポリープなどの喉頭微細手術58例、喉頭麻痺に対する音声改善手術9例、甲状腺手術66例、甲状腺を除く頭頸部がん手術61例、がんを除く頭頸部腫瘍手術45例などとなっている ★耳科手術は慢性中耳炎・真珠腫性中耳炎に対する鼓室形成手術、耳硬化症に対するアブミ骨手術、両側高度感音難聴者に対する人工内耳手術などを精力的に行っている ★頭頸部がんの治療に関しては、主に進行した咽頭・喉頭がんに対して放射線科と協力して、がんに分布する栄養血管にカテーテルを挿入し、抗がん剤を選択的に注入する超選択的動注化学療法を放射線療法と組み合わせて行っている。この治療法による3年生存率は喉頭がんで72.5%、下咽頭がんで70.5%と非常に良好であり、喉頭温存率は喉頭がんで66.4%、下咽頭がんで89.6%と機能温存にも貢献している ★NK/T細胞リンパ腫は、確定診断に苦慮し予後不良となることが多いが、当科ではこの疾患に先駆的に取り組んでおり、03年より放射線併用浅側頭動脈動注化学療法を導入し100%の寛解率を得ている ★扁桃疾患は当教室の得意分野のひとつであり、掌蹠膿疱症やIgA腎症などの扁桃病巣疾患に対して積極的に扁桃摘出術を行い、非常に高い有効率をあげている ★音声障害に対する外科的治療も積極的に行っている。甲状腺がんなどの手術後合併症のひとつである反回神経麻痺による音声障害に対して、甲状軟骨形成術・披裂軟骨内転術などの音声改善手術を行い、非常に良好な成績をあげている ★ナビゲーションシステムを副鼻腔手術や中耳手術に取り入れている。この方法によって、難易度の高い症例においても手術合併症の軽減と、より確実な治療効果をあげられるようになった ★内視鏡補助下甲状腺手術を最近導入している。この手術法は頸部に皮膚切開創が残らず、審美的に非常に優れた治療方法である ★睡眠時無呼吸症候群に対して、当院では「睡眠クリニック」を開設し、内科、精神神経科、口腔外科、小児科と共同して集学的治療を行っている。詳細は当科ホームページ(http://www.asahikawa-med.ac.jp/dept/mc/oto/)を参照。 |
医療設備 |
MRI、CT、PET、超音波診断装置、超音波扁桃誘発装置、電子内視鏡、音声機能検査装置、ストロボスコープ、他覚的聴力検査機器、耳鳴検査装置、人工内耳マッピングシステム、平衡機能検査機器、顔面神経機能検査機器、鼻腔通気度計、サージトロン、KTPレーザー、マイクロデブリッダー、嗅覚検査機器、電気味覚計、睡眠時無呼吸検査装置、高気圧酸素療法室。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 △
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 北海道」(ライフ企画 2010年6月)
- 消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
- 呼吸器センター(呼吸器内科)
- 呼吸器センター(呼吸器外科)
- 循環・呼吸・神経病態内科
- 腎臓内科
- 小児科
- 小児外科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 第3内科(血液・腫瘍内科)
- 膠原病内科
- 外科(乳腺内分泌外科)
- 放射線科
歯科口腔外科
分野 |
歯科口腔外科 |
|---|---|
特色 |
唇顎口蓋裂、顎変形症、悪性腫瘍などの高度専門診療、救急医療など口腔外科的治療を積極的に行い、地域の中核病院として、地域に根ざした医療を提供するとともに、安全・安心な医療を提供している。また、基礎研究として骨再生に関する研究を積極的に行っており、先進的な研究成果を臨床応用し、患者のQuality of Life(QOL:生活の質)の向上に努めている。 |
症例数 |
08年における初診症例は1,060症例。年間入院症例は227例で、そのうち手術を要した症例は188例であった。入院手術内訳は、唇顎口蓋裂は19例、悪性腫瘍は15例、顎変形症は15例、その他は良性腫瘍、嚢胞、骨折などであった ★唇顎口蓋裂に対しては、成長発育を阻害せず、かつ審美、咀嚼、言語の機能を回復させられるように小児科、耳鼻咽喉科とも連携し治療を行っている ★さらに、近年増加傾向にある口腔領域の異常感や慢性化した痛みなどに対して、専門的な心身医学的治療を行っている。また、ドライマウスや特殊な口腔粘膜疾患などに対し、いわゆる口腔内科学的診断・治療を積極的に行っている ★口腔悪性腫瘍に対しては手術療法を主体とし、必要に応じて放射線治療および化学療法等を選択している。超進行がんに関しては、遊離組織移植による即時再建も行い、患者のQOLの向上に努めている。 |
医療設備 |
CT、MRI、PET、超音波診断装置、リニアック、炭酸ガスレーザー、ヤグレーザー、インプラント・顎変形症用画像解析システムなどを備えている。 |
- セカンドオピニオン受入 △
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 北海道」(ライフ企画 2010年6月)
- 消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
- 呼吸器センター(呼吸器内科)
- 呼吸器センター(呼吸器外科)
- 循環・呼吸・神経病態内科
- 腎臓内科
- 小児科
- 小児外科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 第3内科(血液・腫瘍内科)
- 膠原病内科
- 外科(乳腺内分泌外科)
- 放射線科
第3内科(血液・腫瘍内科)
分野 |
血液内科 |
|---|---|
特色 |
道北・道東の血液・腫瘍患者の拠点病院として、多くの未治療患者が遠方より紹介・受診される地域的特性の他、当講座の消化器内科と連携した消化管病変を有する造血器腫瘍患者の精力的な診断・治療も大きな特徴である。日本血液学会認定施設、骨髄移植認定施設。 |
症例数 |
血液疾患の新患者数は年間約200人で、大半は関連病院などからの紹介患者である。通院患者は月間約400人。入院患者は常時20人程度おり、08年度年間延べ入院患者は213人である。その内訳は、悪性リンパ腫55%、急性白血病10%、慢性骨髄性白血病7%、多発性骨髄腫12%、その他の造血器腫瘍8%、非造血器腫瘍8%である ★悪性リンパ腫は、抗体療法(リツキシマブ)を併用した化学療法を日常的に行っている他、放射性免疫療法薬(ゼバリン)の実施可能施設となっている。また65歳以下の患者に対しては、完治を目指した自家末梢血幹細胞移植も精力的に行っている。さらに、当講座の消化器内科とも緊密に連携し、最新の自家蛍光内視鏡やカプセル内視鏡・小腸内視鏡を駆使して、消化管病変を有する悪性リンパ腫を始めとする各種血液疾患の診断・治療に力を入れている。特に、微小病変の検出、正確な病期診断や治療効果判定に大きく寄与しており、当該分野における知見を国内・外に広く情報発信している ★急性白血病は、日本成人白血病研究グループ(JALSG)の成果に基づき、化学療法を施行している。特に、病院独自に染色体分析・遺伝子検査を実施できる細胞分析室(臨床検査・輸血部所属)の協力を得て、各病型の迅速な診断および治療方針の決定を行っている ★慢性骨髄性白血病に関しては、イマチニブを用いた分子標的治療により高い治療成績をあげている他、東日本CML研究グループにも加盟し、イマチニブ耐性患者における新規治療薬を用いた臨床試験も積極的に行っている ★多発性骨髄腫では、標準的化学療法はもとより、サリドマイド・ボルテゾミブなどの分子標的治療を含めた化学療法や自家移植を日常的に行っている ★一般血液疾患に関しては、特に鉄代謝に関する当講座の豊富な基礎的・臨床的研究基盤に基づいた患者治療に力を入れている。日本鉄バイオサイエンス学会作成の「鉄剤の適正使用による貧血治療指針」(作成委員:高後教授)に基づいた鉄欠乏性貧血の予防・治療を行っている他、基礎研究分野とも連携して、慢性疾患に伴う貧血や輸血後鉄過剰症などの病態解明や診断・治療も精力的に行っている ★造血器疾患に対する同種造血幹細胞移植も症例数を重ねており、09年11月現在50例(骨髄16例、末梢血16例、臍帯血18例)となった。近年では骨髄非破壊的移植の症例数も増加(19例)し、高齢者血液疾患に対しても積極的な治療を展開している。さらに、抗がん化学療法プロトコールの院内登録制に基づいた外来化学療法を積極的に施行しており、患者さんのニーズを取り入れQOL(Quality of Life:生活の質)を高めるための治療を実践している。また当院では、経口抗がん剤の院内ガイドラインも整備し、造血器腫瘍患者のみならず、がん薬物療法全般に対して安全かつ快適な診療を提供している ★関連病院との連携=当科の血液疾患の関連病院である旭川厚生病院や慶友会吉田病院とも密に連携して、抗がん化学療法を始めとする造血器疾患患者の診断・治療を行っている。また、市内血液内科医師による症例検討会(旭川血液カンファレンス)での情報交換を通じて、難治症例の治療指針の検討なども行っている。 |
医療設備 |
無菌室2床、血液病床20床。輸血・細胞療法部門とも連携した末梢血幹細胞採取設備は完備している。外来化学療法部門(点滴センター:12床)もフル稼働している。放射線治療部門に加えてPET検査やゼバリン療法も可能な核医学部門も充実し、さらには光学医療診療部における最新の内視鏡設備も完備するなど、血液疾患の診断・治療に必須の医療設備および十分な体制下で診療を行っている。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 北海道」(ライフ企画 2010年6月)
- 消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
- 呼吸器センター(呼吸器内科)
- 呼吸器センター(呼吸器外科)
- 循環・呼吸・神経病態内科
- 腎臓内科
- 小児科
- 小児外科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 第3内科(血液・腫瘍内科)
- 膠原病内科
- 外科(乳腺内分泌外科)
- 放射線科
膠原病内科
分野 |
リウマチ・膠原病内科 |
|---|---|
特色 |
北海道の中で道北・道東地域では数少ないリウマチ・膠原病を専門としている内科であり、旭川市内はもとより、非常に広い地域から専門診療を求め紹介通院されている。大学病院の特色を生かし、他科とも積極的に連携し、様々な症状を呈する膠原病やリウマチ性疾患を総合的に診療していくことを目標としている。また、日本リウマチ学会認定教育施設として、リウマチ専門医の育成にも力を入れるとともに、日本リウマチ友の会や全国膠原病友の会とも連携をして、地域医療への貢献も目指している。さらに、内分泌内科も併診していることから、自己免疫性疾患である膠原病に合併しやすい橋本病など、多くの甲状腺疾患も同一診療科で診療可能なことも当科の特色の一つである。 |
症例数 |
月間平均外来数(08年度)は約950人、1日あたりの平均入院患者数は約20人である。現在、外来通院されている方々の疾患別内訳は、関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎・皮膚筋炎、結節性多発動脈炎やアレルギー性肉芽腫性血管炎などの血管炎症候群、混合性結合組織病、ベーチェット病、シェーグレン症候群などから、リウマチ性多発筋痛症、成人発症スティル病、抗リン脂質抗体症候群などである。さらに、リウマチ性疾患における内科治療を幅広く担当し、強直性脊椎炎や乾癬性関節炎などの血清反応陰性脊椎関節症や掌蹠嚢胞症性関節炎などから、変形性関節症や骨粗鬆症に至る骨関節関連疾患を診療している。また、不明熱や関節痛など他院で診断がつきにくい方々や自己抗体陽性の精査などで紹介来院される方も多い ★関節リウマチについては、日常生活レベルの向上と関節破壊進行の阻止を主眼に、日本あるいはアメリカリウマチ学会の治療ガイドラインに準じた上で、それぞれのニーズに合わせた的確な治療を心がけている。早期診断のために、関節のMRI検査や超音波検査などを用い、また治療においても、早期からメトトレキサート治療を中心に抗リウマチ薬物療法を開始し、必要に応じて生物学的製剤(抗サイトカイン療法)や白血球除去療法なども積極的に使用している。さらに、滑膜切除術や人工関節置換術においては、当院整形外科とも密接に連携しているために、同一病院内で実施可能である ★その他の膠原病についても、的確な診断のもと的確な治療を心がけている。特に皮膚病変、肺病変あるいは腎病変などに対しては、正確な診断確定や治療方針決定のために、当院の皮膚科、呼吸器内科、腎臓内科や泌尿器科と密接に連携して、生検を積極的に実施している。一般に膠原病の治療において、骨関節症状や発熱だけの場合と糸球体腎炎や胸膜炎・腹膜炎あるいは間質性肺炎を有する場合、さらに膠原病の中でも病気の種類によって使用されるステロイド量や免疫抑制薬の種類が異なることから、副作用を最小限にとどめて効果を最大限に出すような治療方針を心がけている ★その他のリウマチ性疾患の中では、乾癬性関節炎、反応性関節炎あるいは掌蹠嚢胞症性関節炎などが多く、これらの疾患は原因不明の関節炎として紹介されてくることもある。的確な診断のもと、疾患特異的な治療を開始することで高率に関節痛が消失している。さらに、関節リウマチに合併したり、あるいはステロイド治療によって誘発される骨粗鬆症治療にも力を入れている ★その他、不明熱に対しては膠原病疾患だけでなく、慢性感染症や造血器腫瘍をはじめとした悪性腫瘍など、様々な疾患を念頭に置くことが重要であるため、各科との協力体制のもと全身精査にも心がけている。 |
医療設備 |
PET、MRI、CT、ヘリカルCT、超音波検査、RI検査、骨密度測定装置(DEXA)、各種内視鏡、血管造影検査など、リウマチ性疾患や合併症・併発症などの診断治療に必要な医療機器はすべて整っている。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 △
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 北海道」(ライフ企画 2010年6月)
- 消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
- 呼吸器センター(呼吸器内科)
- 呼吸器センター(呼吸器外科)
- 循環・呼吸・神経病態内科
- 腎臓内科
- 小児科
- 小児外科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 第3内科(血液・腫瘍内科)
- 膠原病内科
- 外科(乳腺内分泌外科)
- 放射線科
外科(乳腺内分泌外科)
分野 |
乳腺・内分泌外科 |
|---|---|
特色 |
呼吸器センター(大崎能伸呼吸器内科教授)の外科部門として診療している。北海道対がん協会、旭川がん検診センター、和田産婦人科医院と協力し、乳がんの早期発見を目指している。手術、放射線照射の局所治療と全身療法である薬物療法を、時代のエビデンスを重視して実行している。外来化学療法の設備も整っているほか、リンパ浮腫外来も開設し、リンパ浮腫に対する予防と治療を施行している。 |
症例数 |
08年は221例の手術症例を施行した。原発性乳がんは165例、そのうち乳房温存手術137例(83%)であった。術前N0(所属リンパ節転移なし)症例に対して、ICG蛍光測定法を併用した色素法によるセンチネルリンパ節生検を行っている。その他、インプラントを使用した乳房再建術5例、良性乳腺腫瘍24例、腋窩郭清、LN生検等27例に施行した ★非触知のMMG上カテゴリー3以上の微細石灰化病変に対し、マンモトーム生検を積極的に行っている。過去5年間に231例に施行、61例(23.4%)が乳がん症例であり、85%がDCIS(非浸潤がん)症例であった ★局所進行乳がんに対する初期全身療法(PST)は10~15%に施行している。完遂例93%、乳房温存率76.4%、現在HER2陽性症例に対するトラスツズマブ併用を開始した ★一般的に乳房切除を選択するE領域乳がんに対する乳頭乳輪合併切除乳房温存手術も積極的に施行し、過去3年間の乳房温存率は78.6%であった ★10年生存率はI期96%、II期88%。 |
医療設備 |
デジタルMMG(マンモグラフィ)、US、CT、PET-CT、MRI、核医学検査、マンモトーム、赤外観察カメラ(PDE)、放射線治療装置など。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 ○
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 北海道」(ライフ企画 2010年6月)
- 消化器・血液腫瘍制御内科(第3内科)
- 呼吸器センター(呼吸器内科)
- 呼吸器センター(呼吸器外科)
- 循環・呼吸・神経病態内科
- 腎臓内科
- 小児科
- 小児外科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科
- 第3内科(血液・腫瘍内科)
- 膠原病内科
- 外科(乳腺内分泌外科)
- 放射線科
放射線科
分野 |
放射線科 |
|---|---|
特色 |
11人が日本医学放射線学会認定の専門医で、このうち6人は核医学学会、放射線腫瘍学会、IVR学会などの専門医、認定医となっている。画像診断においては、CT、MRI、核医学検査(PET、SPECT)の他、放射線科施行の超音波検査、血管造影・IVRのほぼ全例に対し当日中に画像診断レポートを作成し、各科に情報を提供している。休日中に救急部依頼で撮像されたCT、MRIに対しても極力迅速に画像診断レポートを作成し、診断の質を高めるようにしている。また、旭川医科大学全体で取り組む遠隔医療では、道北・道東地区の病院を中心に8病院の画像診断(主にCT、MRI)を支援している。治療では、頭頸部進行がんに対する超大量動注化学療法併用放射線治療、前立腺がんに対する強度変調放射線治療(IMRT)、転移性脳腫瘍に対する定位放射線照射に積極的に取り組み、形態と機能を温存する治療に取り組んでいる。また、道北・道東地区で唯一のラジオアイソトープ(RI)内用療法専用の病床を2床有し、甲状腺がん、甲状腺機能亢進症の治療を行っている。また、09年より低悪性度の悪性リンパ腫や転移性骨腫瘍に対する内用療法も開始された。IVRでは、子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓療法や静脈奇形(血管腫)に対する硬化療法を実施している他、救急医療における止血目的の動脈塞栓術にも24時間対応している。 |
症例数 |
★08年度の検査件数は単純撮影187,964件、CT 18,827件、MRI 6,906件、核医学3,511件、血管造影およびIVR(放射線科施行分)329件、超音波検査(放射線科施行分)1,256件などであった ★血管造影・IVRでは、消化器内科との協力で121件の選択的肝動注化学塞栓療法を行っている。また、03年より当科放射線治療医、耳鼻咽喉科との協力で進行頭頸部がんに対する超大量動注化学療法併用放射線治療をこれまでに120例程施行し、全身化学療法併用放射線治療と比較し高い局所制御率を得ており、機能形態温存が多くで可能となっている。この治療では、疾患特異的3年生存率はStageIVを中心とする下咽頭がんで59%、中咽頭がんで67%となっている。その他、特殊な分野としては子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術や静脈奇形(血管腫)に対する硬化療法を各科と協力しながら施行している ★核医学検査では、SPECTによる通常の検査の他、09年7月よりPET-CTが導入され、がんのステージング、治療効果判定、予後予測などの正確な診断に威力を発揮している。RI内用療法では、甲状腺がんの治療を年間66件程施行し、内科的治療が困難となった甲状腺機能亢進症に対する内用療法も年間17件程施行している ★放射線治療においては、08年度の新患者数は376人、総治療患者数440人で、主な内訳は乳がん118人、骨転移86人、頭頸部がん65人、中枢神経系の悪性疾患49人、リンパ腫/白血病44人、前立腺がん19人、食道がん13人、婦人科腫瘍10人となっている。外部照射は、乳腺外科と協力した乳がんの乳房温存術後照射の患者数が最も多いが、様々な領域の悪性腫瘍治療に各科と協力しながら対応している。特殊な外部照射としては、転移性脳腫瘍に対する定位放射線照射を年に20~30件程施行し、QOL向上に大きく貢献している。前立腺がん、頭頸部がん、原発性脳腫瘍に対しては症例に応じてIMRTも施行している。また、09年よりI期原発性肺がんや孤発性転移性肺がんに対して、症例によって体幹部定位放射線治療も開始した。外部照射以外ではIr(イリジウム)-192高線量率小線源治療を施行しており、子宮頸がんや早期食道がんの腔内照射に対応している。基本的に外来通院で通常通りの生活を維持しながら放射線治療を行うことを目標としている。 |
医療設備 |
MRI 2台、CT 2台、血管造影装置2台、SPECT 3台、PET-CT、骨密度測定装置、リニアック2台(術中照射設備あり)、イリジウム高線量率小線源装置、RI治療病室2室、一般病床5床。 |
- セカンドオピニオン受入 △
- 初診予約 △
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 北海道」(ライフ企画 2010年6月)
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
旭川医科大学病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
旭川医科大学病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 名医の推薦分野について
- 名医の推薦分野に掲載する情報は、ライフ企画が独自に調査、取材し、出版する書籍、「医者がすすめる専門病院」「専門医が選んだ★印ホームドクター」から転載するものです。出版時期は、それぞれの情報ごとに記載しています。全ての情報は法人としてのQLifeの見解を示すものではなく、内容を完全に保証するものではありません。
 QLife会員になると特典多数!
QLife会員になると特典多数!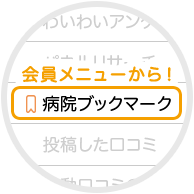

診療科目:産婦人科
2018年09月23日投稿
先生も丁寧だし、看護師さんも優しく、入院期間中は安心して過ごすことができました。出産でトラブルがあった場合は、NICUが対応してくれることが、病院を選んだ理由でした。続きをみる