群馬大学医学部附属病院(群馬県前橋市)が名医に推薦されている分野
専門医より推薦を受けた診療科目・診療領域
群馬大学医学部附属病院は、複数の有名専門医(※)の間で「自分や家族がかかりたい」と推薦されています。
このページでは、専門医より推薦を受けた分野(科目、領域)の特色や症例数、所属している医師について取材・調査回答書より記載しています。
※推薦、選定して頂いた有名専門医の一覧表
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
分野 |
消化器・一般内科 |
|---|---|
特色 |
肝疾患全般、特に慢性肝炎の特殊インターフェロン治療、肝癌の内科的治療、食道、胃、大腸疾患の内視鏡的診断および内視鏡的治療、胆膵の悪性腫瘍とそれによる閉塞性黄疸に対する内視鏡的診断、治療を主体に行っている。消化器内科として患者さんのQOLを優先した診断、治療を促進すると共に、手術適応についても各種外科系とのカンファレンスを通して検討し、肝臓移植も含めた適応例は外科へ適宜紹介している。また、肝臓癌の治療にラジオ波焼灼療法を用いて効果をあげている。さらに、消化管内圧測定を行い、種々の上部消化管疾患に対して有効な治療法を選択している。 |
症例数 |
肝疾患としては1年間平均30例のC型肝炎をインターフェロンにを中心に治療し、全体で有効率66%の好成績をあげている。難治性のウイルス保持者に対しても、インターフェロン大量ないしは特殊亜鉛併用療法を用いて有効率45%を達成している。最近5年間で100例の肝癌患者に延べ200回の治療が行われ、手術率は16%、その他、大部分の肝癌は肝動脈塞栓療法(TAE)、アルコール注入療法(PEIT)を主体に非手術的治療を施行し、全体で5年生存率35%、小肝癌でかつ肝硬変の軽度な患者での5年生存率は60%を超える。これらの治療も不可能な大型肝癌や、多発肝癌に対しては肝動脈塞栓療法を主体に治療を行い、5年生存率25%を得ている。最近ではラジオ波を用いた局所療法で手術に匹敵する治療効果を得ている。一種類の治療法ではなく、各々の治療法の特徴を駆使した集学的治療を旨としている。食道静脈瘤に対しては、内視鏡的硬化療法および結紮術を施行し、平均で85%以上の静脈瘤の改善が得られている。肝癌合併の食道静脈瘤に対しても、これらの内視鏡を用いた予防的治療により、静脈瘤破裂による死亡はほとんどみられなくなってきた ★消化管内圧測定、インピーダンス法、13C胃排出測定などを用いた消化管の機能分析では世界的に評価されており、アカラシアなどの原発性食道運動障害(ものが飲み込めない)や、膠原病に伴う消化管機能異常の疑われる場合などに年間約40例の食道・胃内圧測定を施行している。治療としても内視鏡的食道拡張術が年間約10例に施行されている。悪性腫瘍の内視鏡治療では、早期胃癌内視鏡的粘膜切除術治療件数約20例、早期胃癌内視鏡的粘膜下層剥離術約5例、アルゴンプラズマ凝固療法約5例、早期食道癌内視鏡的粘膜切除術約5例が行われている。2000年からは内視鏡的粘膜切除術や手術不能例に内視鏡的光線力学療法(Photodynamic therapy)も導入している ★大腸内視鏡検査(CF)件数は年間約1000例に及び、正確かつ安全な手技習得を目標として日々研鑽を重ねている。近年、大腸癌や炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎やクローン病)は増加傾向にあり、診断、治療を目的としたCFの需要は高まりつつある。大腸癌を含む大腸腫瘍に対して、ここ数年で内視鏡による診断および治療の進歩がみられた。特殊光(NBIやAFIなど)観察により腫瘍の質的診断はより正確なものとなり、新しい治療用デバイスや技術の導入により内視鏡治療はより確実、より容易なものとなった。炎症性腸疾患に対しては厚生労働省主催の調査研究班が示す治療指針(案)に従い、診療を行っている。難治性潰瘍性大腸炎に対する血球除去療法やシクロスポリンなどの免疫制御剤投与、クローン病に対する抗TNF-α抗体療法なども積極的に行い、寛解導入および維持を図る。現在、潰瘍性大腸炎約100例、クローン病約40例が当科にて治療を受けている。その他、過敏性腸症候群も増加している疾患であり、外来で診療にあたる機会が増えている ★内視鏡的逆行性膵胆管造影検査は年間約130例施行している。近年CTやMRI(MRCP)の普及により造影のみの検査は減少傾向にあるが、内視鏡的乳頭括約筋切開術(EST)約30例、内視鏡的胆管ドレナージ術(EBD)約50例といった治療目的の検査が半数以上を占めている。胆管腫瘍・膵腫瘍の術前検査や、総胆管結石、胆道狭窄症に対して、治療内視鏡(EST、EBD)を主に行っている。また近年、胆膵の悪性疾患は、以前より化学療法による予後の延長が期待されてきており、悪性腫瘍による閉塞性黄疸に対しても積極的にドレナージ治療を行い、QOLの向上に努めている。 |
医療設備 |
CT、血管造影下CT、MRI、3次元エコー、炭酸ガス・アルゴンレーザー、超音波内視鏡、ラジオ波焼灼装置。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
分野 |
呼吸器内科 |
|---|---|
特色 |
当科は日本呼吸器学会、日本アレルギー学会、日本臨床腫瘍学会、日本呼吸器内視鏡学会、日本感染症学会の認定施設である。呼吸器疾患全般、特に、肺癌、間質性肺炎、気管支喘息、COPD、呼吸器感染症の高度・専門的な診療を行い、優れた治療成績を出している。診療に当たってはインフォームド・コンセントに基づき、患者とのコミュニケーションを大切にしながら治療を行っている。 |
症例数 |
初診患者は紹介患者が主体である。外来患者数は1日平均約100人 ★肺癌は年間入院患者数約80例。気管支鏡検査(年間約130件)による経気管支肺生検、超音波気管支鏡ガイド下針生検や画像診断部と連携したCTガイド下経皮肺針生検による確定診断を積極的に行っている。中枢気管支病変の観察には蛍光気管支鏡検査も併用している。FDG-PET-CTを含めた通常の画像診断に加えて、アミノ酸を利用したFAMT-PETも用いて、肺癌の正確な病期診断を行い、手術可能な患者さんは、呼吸器外科と連携して治療を進めている。また、手術不能進行非小細胞肺癌の患者さんには化学放射線療法、化学療法、さらにEGFR遺伝子の変異解析に基づいた EGFRチロシンキナーゼ阻害剤による分子標的治療を行っている。小細胞肺癌の患者さんに対しては、抗癌剤による化学療法あるいは化学療放射線療法を行い、ほとんどの例で良好な腫瘍縮小効果を得ている。患者さんのQOLの向上を図るため、外来化学療法も積極的に行っている ★特発性間質性肺炎、膠原病肺、過敏性肺炎、好酸球性肺炎、サルコイドーシスでは気管支肺胞洗浄による細胞成分の解析、経気管支肺生検により迅速、確実な診断、治療を行っている。画像上、特発性肺線維症と診断できない間質性肺炎症例では、病理部、呼吸器外科と連携して胸腔鏡下肺生検を行い、正確な病理診断に基づく薬物療法を行い、治療成績は向上している ★気管支喘息の診断には呼気中一酸化窒素濃度測定を取り入れ、気道過敏性検査も行っている。治療管理には喘息日誌の記載、ピークフローの自己測定、通常の呼吸機能測定のほか、インパルスオシレーション法による気道抵抗測定を用いており、ガイドラインに基づく吸入ステロイド薬を中心とした治療を行い、効果をあげている。通常の治療では症状をコントロールするのが難しい気管支喘息患者さんにはインンフォームド・コンセントを得たうえで新規治療法の開発を行っている ★COPDでは、呼吸器疾患以外の疾患で治療中の患者さんにおいても、呼吸機能検査によって積極的に重症度を含めた診断をするとともに、COPDを全身性疾患として捉え、早期よりガイドラインに基づいて吸入薬を主体とした薬物療法を行い、消化器疾患、循環器疾患、糖尿病などの合併症にも注意しながら診療を行っている ★呼吸器感染症として市中肺炎のほか、COPDの感染による増悪などに対して、起炎菌の推定に基づく、迅速かつ適切な化学療法を行い、良好な治療成績を得ている。 |
医療設備 |
マルチスライスCT、PET-CT、MRI、超音波気管支鏡、蛍光気管支鏡など。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
第1外科(呼吸器外科)
分野 |
呼吸器外科 |
|---|---|
特色 |
肺癌をはじめ、縦隔腫瘍、気胸、膿胸など呼吸器外科領域全般にわたる疾患に幅広く対応しており、呼吸器内科、放射線科と連携し、術前術後の便宜を図るとともに、外科治療のみならず集学的治療を積極的に進めている。また、外科療法には、より侵襲の少ない胸腔鏡下手術を積極的に取り入れている。特に、気胸や手掌多汗症に対する胸腔鏡下手術では、短期入院にも対応している。 |
症例数 |
2008年の年間手術症例数は109例で、その内訳は、原発性肺癌の切除数が45例であった。その他、転移性肺腫瘍21例、良性肺腫瘍10例、縦隔腫瘍・重症筋無力症17例、気胸3例などである。肺癌外科療法は、胸腔鏡下肺葉切除術にも積極的に取り組んでいる。従来手術適応がないとされていた進行肺癌に対しては、呼吸器内科、放射線科と連携し、外科治療のみならず、化学療法や放射線療法を併用した集学的治療を積極的に取り入れ、治療成績の向上に努めている。また、自然気胸や肺嚢胞、肺末梢病変などの良性肺疾患や胸膜疾患に対して、術後の痛みが少なく入院期間も短くてすむ胸腔鏡下手術を積極的に施行している。気胸に対する胸腔鏡下ブラ切除や手掌多汗症に対する胸腔鏡下交感神経焼灼術は3~5日間の短期入院手術にも対応している。治療成績は、気胸の再発率は9.2%、手掌多汗症に対する手術では全例に症状の改善が認められている。手術以外に気管支鏡下レーザー焼灼術、気道ステント留置術なども行っている。 |
医療設備 |
CT、MRI、DSA、PET、レーザー、リニアックなど、医学部附属病院として必要な設備は完備している。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
第2外科(呼吸器外科)
分野 |
呼吸器外科 |
|---|---|
特色 |
肺癌を中心に、縦隔腫瘍、肺良性腫瘍、気胸、膿胸、胸部外傷まで幅広く診療を行っている。特に肺癌においては、低侵襲で根治性の高い胸腔鏡下手術(hybrid VATS)を中心に行っている。2cm以下の肺癌においては縮小手術として肺区域切除を積極的に取り入れ、機能温存と根治性の両立を目指している。同診療科内の心臓血管外科、消化器外科、乳腺・内分泌外科と連携し、肺癌・縦隔腫瘍などに対する拡大手術も積極的に行っている。肺癌においてはEGFR、K-rasなどの遺伝子変異診断を利用した個別化治療を行っている。 |
症例数 |
肺癌症例数:2006年43例、2007年54例、2008年59例。肺癌の5年生存率、( )内は全国平均:IA期85.7%(83.3%)、IB期72.5%(66.4%)、IIA期66.0%(60.1%)、IIB期53.2%(47.2%)、IIIA期33.5%(32.8%)、IIIB期58.2%(30.4%)、IV期0%(23.2%) 。 |
医療設備 |
手術室に隣接してICUを完備。病理医が常勤しており術中迅速診断に常時対応。FDG-PET装置を3台完備。2010年度より重粒子線治療施設が稼働予定。CTガイド下ラジオ波焼灼術、抗癌剤の動注療法にも対応。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
第2外科(心臓血管外科)
分野 |
心臓血管外科 |
|---|---|
特色 |
大学病院である性格から、臨床および研究の両方に努めている。研究は心・肺移植における臓器保存、再灌流傷害をメインテーマとしている。他には開心術における心筋保護、弓部大動脈手術における脳保護などに関して行い、欧米の学会雑誌等でその成果を発表している。腹部大動脈瘤に対する超音波およびCTを用いた検診を世界に先駆けて導入し、県下の動脈破裂症例数の減少に寄与したと考える。 |
症例数 |
年間70例前後の心臓血管外科手術を施行している ★手術死亡率は緊急手術も含め全体で約4%であった。冠動脈手術、弁膜症手術、胸部・腹部大動脈などに対する大血管手術、先天性心疾患を中心に行っている ★閉塞性動脈硬化症、下肢静脈瘤などの末梢血管外科手術も行っている ★心臓血管外科分野の新しい治療法である不整脈手術(Maze)、弁形成手術、体外循環を用いない心臓手術や低侵襲手術(MICS)、重症心不全に対する手術などを既に導入している。これらの手術は今後も積極的に行っていく方針である ★大学病院という施設の特徴を生かし、同じく第2外科の消化器グループ、呼吸器グループ、乳腺・内分泌グループあるいは他科と連携して、集学的治療を要する手術を円滑に行っている ★治療方針は、循環器内科と定期的なカンファレンスを行い、活発な討論を経て決定している ★緊急手術の生命予後の改善には、患者搬送よび手術開始が速やかであることが必須である。そのため、当科では県下の関連施設と連携している。 |
医療設備 |
MRI、CT、心エコー検査、血管造影検査、各種核医学検査。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
整形外科
分野 |
整形外科 |
|---|---|
特色 |
肩関節、手関節、股関節、膝関節、足関節など、関節機能外科を中心として、脊椎も含めた部位別専門外来を設け、スポーツなどの外傷や高齢社会に伴って増加している変性疾患、そして炎症疾患等を幅広く取り扱っている。また、関節リウマチや、四肢における骨軟部腫瘍病変に対する疾患に対しても専門的な診療を行っている。各疾患ともに手術療法が主体ではあるが、長期的な機能の改善とその維持を目標として診療方針を決定し、リハビリを含めた後療法をおろそかにせず、QOLを考慮した手術に努めている。 |
症例数 |
年間の全手術数は約800例(2008年度) ★肩関節に対する手術は年間110例、主に肩腱板断裂や反復性肩関節脱臼に対する肩関節形成術を行っており、そのほとんどは肩関節鏡を用いた低侵襲手術で、治療期間の短縮・早期の社会復帰を目指している ★関節リウマチの治療の第一選択は薬物療法で、抗リウマチ剤や消炎鎮痛剤が用いられるが、近年登場した生物学的製剤も症状にあわせて使用している。第二選択として鏡視下滑膜切除術や関節形成術などの手術療法を考慮している。また、GradeIII、特に下肢の関節には人工関節置換術を適用している ★膝関節手術は年間約60例行っている。変形性膝関節症に対しては人工膝関節置換術、高位脛骨骨切り術を中心に行っている。膝靱帯損傷に対しては、症例により靱帯再建術、保存的治療を選択し、満足のいく成績を得ている。膝半月鏡視下手術は1977年より施行しており、その長期成績より、可及的半月板を温存する方法を選択している ★骨軟部腫瘍外来では、定期的経過観察を行っている良性疾患から、高度な診断治療を必要とする骨軟部肉腫の診療までを行っている。MRIとCTを行い、全身の病変の検索のためにポジトロンCTを活用して、術前診断の的確性を高めている。年間手術件数は約170例である。悪性腫瘍に対しては生命予後を最重要課題とした上で、長期的機能維持を考慮した患肢温存に努めた手術を行っている。治療は手術療法を主体としているが、化学療法も行い、放射線科との連携を密にして、放射線療法の適応も考慮した多方面からの治療に努めている。また、QOLを考慮したインフォームド・コンセントを基本とした治療を展開し、骨軟部原発悪性腫瘍の5年生存率は70%である ★股関節に対する手術数は年間約90例で、人工股関節手術、寛骨臼回転骨切り術、小児先天性股関節脱臼手術、外傷および感染症に対する手術を行っている。特に、変性疾患である変形性股関節症に対しては、年齢・病期により、関節温存と人工関節手術の適応を慎重に検討し、人工関節手術の際にはインフォームド・コンセントを特に重視している ★脊椎外科の対象疾患としては、頭蓋頸椎移行部疾患、頸髄症、後縦靱帯骨化症、椎間板ヘルニア(内視鏡下含む)、脊椎管狭窄症、側彎症、腰椎分離すべり症、脊椎炎、脊髄腫瘍等の手術を行っている。術式は、疾患の性質、各々の脊椎の形態と機能、および神経学的所見を基に前方法、後方法を使い分けている年間手術件数は約160例である ★手の外科で扱う手術数は、年間40~50例である。上肢の先天奇形、絞扼性神経障害、肘の鏡視下手術などを行っている。また、デイサージャリーも最近積極的に行っている。マイクロサージャリーを用いた腫瘍関連の再建術も、年間数例行っている。 |
医療設備 |
MRI、CT、DSA、超音波、ポジトロンCT。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
産婦人科
分野 |
産婦人科 |
|---|---|
特色 |
産婦人科のほぼ全域を取り扱っている。専門外来として、リプロダクション(不妊・体外受精)外来、腫瘍外来、ハイリスク妊婦外来、不育症外来、内膜症外来を開設している。最近、助産師による母乳外来も開設した。2009年より電子カルテが導入され、再診受付・カルテ記載・画像保存・処方・検査・予約・会計は、コンピューターシステムにより運営されており、待ち時間の短縮化と診療の効率化が図られている。2010年度よりリプロダクション外来は妊婦や腫瘍の患者とは別の棟に移転し、きめ細かな診療を行う予定である。 |
症例数 |
1年間の延べ外来症例数は約34,000例、入院数は婦人科が360例、産科が700例であり、また、分娩数は年間平均330例で、その多くが合併症を有するハイリスク妊娠である ★リプロダクション外来=生殖医療指導医のもと一般的なスクリーニング検査を徹底的に行い不妊原因を明らかにした上で、その原因療法を行っている。また、当科では排卵障害を有する不妊症に対し安全な排卵誘発法を開発し、治療に積極的に取り組んでいる。さらに、腹腔鏡検査を積極的に行い、当科で開発した大量通水療法により、最適な治療方針を決定することで、高い妊娠率を誇っている。体外受精は卵管性不妊や長期不妊など難治性不妊例に対し、治療を行っている。治療を入院ベースから外来ベースに移し、より多くの症例を受け入れている。近々、不妊患者が妊婦と顔をあわさないように配慮するためリプロダクション外来として、産婦人科外来から独立した場所に移転する予定である。最近は男性不妊に対する治療も積極的に行い、泌尿器科と連携した治療も年々増加している。また、顕微授精、ホルモン補充療法を用いた凍結胚の解凍移植など最新の技術を積極的に導入しており、30%以上の妊娠率を常時維持している。一方、多胎妊娠の率は減少している ★腫瘍外来=腫瘍患者の総合的なフォローアップのために開設された。細胞診で異常のあった症例の精密検査にはじまり、コルポスコピーやレーザーを用いて外来ベースでの初期癌の治療を行っている。また、進行癌患者の術前・術後の系統的な管理を行っている ★妊娠外来=すべての妊婦に対し超音波スクリーニングを行い、胎児の形態異常や子宮内胎児発育遅延症の早期発見に努めている。また、ハイリスク妊婦に対してはカラードプラやパルスドプラを用いた胎児・母体血流測定や、NSTによる胎児胎盤機能検査を頻繁に施行している。分娩棟は周産母子センターにNICUと併設されており、小児科、小児外科と綿密なカンファレンスを通してハイリスク症例の管理や治療を行っている。分娩室には最新の分娩監視システムが導入され、連続した監視とネットワークによるフェイルフリーのシステムが構築されている ★婦人科良性疾患=子宮筋腫、卵巣腫瘍の良性疾患が内視鏡下で行われるようになっている。内視鏡外科学会技術認定医の指導のもと、2007年度の内視鏡下の手術件数は69件で、創の縮小と入院期間の短縮を実現している。その他、レゼクトスコープによる粘膜下筋腫の治療に、最近特に力を入れている ★婦人科悪性疾患=子宮頸癌、子宮内膜癌、卵巣癌など年間で約150例の症例を治療している。診断では、PET、MRI、CTなどの画像診断を組み合わせ、診断精度を上げている。子宮頸癌では上皮内癌や1a期は100%治癒。扁平上皮癌だけでなく最近増加しつつある腺癌や腺扁平上皮癌など予後不良なものまで含めると、1b1期の予後は、88%の5年生存率。1b2期では65%、2期で73%。3a期以上は放射線科の治療になる。子宮内膜癌1a期では100%、1b期で96%。1c期では89%。2期では子宮体部の筋層浸潤度に準じる。3期でも3a期や3b期の予後は86%と良好だが、リンパ節転移陽性の3c期では予後は低下し、46%。卵巣癌は、5年生存率I期90%、II期80%、III期27%、IV期25%で組織型に基づく最適な抗癌剤を選択している。これら悪性腫瘍の治癒率は進行期や組織型に左右されるが、初期のものでは極めて良好な治癒率を維持している ★不育症外来=不育症も系統的検査のうえ、抗凝固療法や免疫療法、ホルモン補充など積極的な治療を行っている ★内膜症外来=ホルモン治療と内視鏡を効率的に組み合わせている。 |
医療設備 |
PET、MRI、CT、カラードプラ、レーザー、子宮鏡、QDRなど。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
小児科
分野 |
小児医療 |
|---|---|
特色 |
当小児科は1944年(昭和19年)3月に設立されたのち、高度先進的医療、地域医療、また卒前卒後の教育機関としての役割を担いつつ、現在に至っている。この間、小児科学教室の教授は松村龍雄から黒梅恭芳、森川昭廣、荒川浩一とバトンタッチされたが、当科は小児期の幅広い年代、すなわち新生児から思春期までの小児を対象としている総合内科学であることを常に念頭に置き、各時代に求められる医療を各専門分野において実践してきた。現在、10の臨床班が相互に協力しあいながら診療を行っている。 |
症例数 |
臨床は血液、呼吸器アレルギー、感染免疫、神経、腎臓、心臓、内分泌、消化器、新生児、精神の10の班に分かれているが、一人ひとりの患者について高度な医療技術をもって対応すべく、ボーダーレスなスタンスをとっている。血液班の骨髄移植、腎臓班の腎生検や透析、神経班の筋生検やポジトロンCTによる脳内代謝の検索、消化器、心臓班のカテーテルやエコーによる検査、内分泌班の各種負荷試験、呼吸器アレルギー班の各種吸入試験や食物負荷試験、新生児班のNICU管理などの基本的な技術に加え、遺伝子解析、機能的画像診断などの新技術を導入し、診断、治療を進めている。病棟では現在、骨髄移植後を含む血液疾患、腎不全、血球貪食症候群、重症新生児仮死、超極小低出生体重児、炎症性腸疾患、膠原病、糖尿病、難治の気管支喘息、けいれん性疾患などの患者が入院している。 |
医療設備 |
重粒子線、MRI、高速ヘリカルCT、ポジトロンCT、各種核医学検査、シネアンギオグラフィ。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
眼科
分野 |
眼科 |
|---|---|
特色 |
主な診療対象は、①眼底疾患:糖尿病網膜症、網膜剥離、黄斑円孔、加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症、黄斑前膜、網膜変性症など、②ぶどう膜炎:原田病、サルコイドーシス、ベーチェット病、③緑内障、④白内障、⑤眼腫瘍、⑥涙器疾患、⑦角膜:潰瘍、角膜移植、⑧斜視弱視、⑨視神経炎、⑩コンタクトレンズ、⑪外傷。このなかで眼底疾患と緑内障は進歩の顕著な分野であり、当科では最先端の治療を行っている。 |
症例数 |
年間の手術は1,800件である。その大半を糖尿病網膜症、網膜剥離、黄斑円孔、加齢黄斑変性などの網膜硝子体疾患が占める ★糖尿病網膜症はまずレーザー光凝固で病勢を沈静化させ、増殖網膜症、黄斑浮腫が増強する場合は硝子体手術を行う。現在、初診時に失明状態になければ、ほとんどを救済しうる ★網膜剥離は若年者では、眼球の外側から治療する従来の方法が主流だが、中高年者では眼球の中から網膜裂孔を閉鎖する硝子体手術の比率が増えてきている。飛蚊症、光視症があったら早めに受診することをすすめたい ★黄斑円孔は中心がゆがむ、見えないという症状がある。硝子体手術によって、当科では95%の円孔閉鎖を得ている ★加齢黄斑変性は最近急増している。高齢者で中心が見えないときはこれを疑う。レーザー光凝固、光線力学的療法、抗VEGF治療などが行われている ★黄斑前膜はゆがんで見えるのが特徴であり、この場合は手術が有効である ★ぶどう膜炎は主にステロイドの局所投与を行う。緑内障は点眼による眼圧のコントロールが治療の主体であるが、コントロール不良例には房水の濾過手術が行われる ★白内障は超音波乳化吸引術と眼内レンズ移植を行う。眼腫瘍は表在性のものは全摘と再建術を行う ★眼窩腫瘍は脳外科と共同治療を行っている。涙器疾患はシリコンチューブ留置や涙嚢鼻腔吻合術などを行う。角膜潰瘍の重症例は入院して集中的治療が必要である。水疱性角膜症、角膜穿孔例では角膜移植の対象となる ★斜視はプリズム眼鏡で両眼視を獲得させてから、外眼筋の短縮または後転により正常の眼位と両眼視機能の回復を目指す ★視神経炎はステロイドのパルス療法が行われる ★県内の外傷の急患は当科が一手に引き受けている。眼球破裂、眼内異物がその主なものである。眼球破裂や眼内異物では眼球壁の縫合の後、白内障があればその手術を行う。多くの場合、硝子体出血、感染、網膜裂孔を伴うため硝子体手術を併用し、出血、感染病巣の除去、異物の摘出を行い、さらに網膜裂孔に対し、レーザー光凝固や強膜輪状締結術を実施する ★白内障は小切開超音波乳化吸引術で核と皮質を吸引し、嚢内に眼内レンズ移植する術式が主流である。大学病院という性質上、さまざまな合併症を持つ白内障の患者さんが多い ★外来受診は紹介状持参が望ましいが、なくてもかまわない。新患には受持医が割り当てられ受持医が予診をとる。その後、教授、助教授もしくは講師がその専門分野の患者を診察する。そこで診断と治療方針が決められ、特殊検査の指示がでる。受持医は蛍光眼底造影などの特殊検査を行う。ときには光凝固などの治療も同日に行う。このため新患は1日がかりとなる。これらのプロセスは大学病院としての診療レベルを維持するためと、本来なら数日かかる診療を1日で済ますための処置であり、患者にとっては高度の医療を受けられることと通院回数が少なくなる利点がある。 |
医療設備 |
光干渉断層計、多局所網膜電図、フルオレセインおよびインドシアニングリーン螢光造影装置、レーザースペックル血流測定装置、超音波生体顕微鏡(UBM)、レーザー光凝固、ヤグレーザー、硝子体手術装置、白内障超音波乳化吸引装置。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
耳鼻咽喉科・頭頸部外科
分野 |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 |
|---|---|
特色 |
めまい、平衡障害患者で診断不能、治療困難とされる他科からの紹介患者が多い。呼吸困難、嚥下困難、めまい、急性感音難聴、顔面神経麻痺、顔面外傷、頸部損傷など耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域の急患に対応している。喉頭癌、上顎癌、咽頭癌、舌癌など頭頸部悪性腫瘍に集学的治療を行っている。 |
症例数 |
年間の全手術数は約350件 ★頭頸部腫瘍患者は入院患者の70%以上を占め、悪性はそのうちの約70%。頭頸部腫瘍の手術は99件(28%)。悪性腫瘍のうち鼻副鼻腔悪性腫瘍は22.2%。下咽頭癌は19.0%、喉頭癌は38.1%、舌癌は6.3%、耳下腺悪性腫瘍は4.8%。そのほか頸部悪性腫瘍、中耳癌、口蓋の悪性腫瘍、中咽頭癌、上咽頭癌、頬粘膜癌、口腔底癌などである。各疾患とも手術療法が主体となるがQOLと予後を考慮し、放射線療法、化学療法を組み合わせた集学的治療を行っている ★慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎などによる伝音難聴をほぼ正常の聴力にまで改善する鼓室形成術は58件(16.6%)で、外耳道形成により術後の空洞の問題をなくすようにしている ★鼻・副鼻腔炎、副鼻腔嚢胞疾患、睡眠時無呼吸症候群、口蓋扁桃、アデノイド、喉頭疾患に対する手術は63件(18.0%)で、術後経過は良好 ★顔面外傷、球後視神経炎、深頸部膿瘍の緊急手術は17件(4.9%) ★難聴が高度なると補聴器を使っても言葉の聞き取りが悪くなる。このような重度難聴者では内耳の働きが悪くなっているので、この内耳の機能を人工的なものに置きかえる。人工内耳埋め込み術を行っている(13件)。 |
医療設備 |
MRI、CT、炭酸ガスレーザー、YAGレーザーなど。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
歯科口腔外科・歯科
分野 |
歯科口腔外科 |
|---|---|
特色 |
当科は群馬県唯一の国立大学法人医学部歯科口腔外科であり、1943年からの長い歴史と伝統を持つ。一次医療機関(開業歯科医院)や二次医療機関(病院歯科)と連携し、すべての口腔外科疾患に対応している。また最近では、マイクロエンドサージャリーを顎骨嚢胞の歯根尖切除に応用し良好な成績を得ている。各領域の専門外来制を敷き、集学的高度医療に力を入れている。特に横尾教授を中心とした顎口腔癌切除後の血管柄付き遊離組織移植を中心とした機能再建は全国のトップレベルの技術と症例数を誇る。一般歯科治療については原則として重篤な全身疾患を有する場合のみ受け付けている。当科では、患者は医師と同等の立場で医師と協力しながら病気と共闘し、医師は「病気を診ずして病人を診る(高木兼寛)」、すなわち患者を全人的に診て治療することを基本としている。当病院は特定機能病院、エイズ拠点病院、がん拠点病院など群馬県の中核病院として機能し、その中で歯科口腔外科は13床の入院病床が確保されている。2011年4月からは日本で3番目の重粒子医学センターが開院し、歯科口腔外科でも新しい顎口腔癌治療の方向性を見いだすべく研究を進めている。 |
症例数 |
年間の初診患者数は2,700人前後、入院患者は250人を上回る。2008年7月に横尾教授が神戸大学医学部口腔外科より赴任し、全く新しい治療体制・体系での臨床がスタートした ★顎口腔癌=初診患者数は年間約70例で、2009年はさらに増加傾向にあり、わが国の口腔外科施設としては最も多い部類に属する。外科療法を第一選択とし、手術は切除チームと再建チームに分かれ、それぞれの専門性を生かした高度の手術が行われている。術後嚥下障害が予測される症例に対しては、耳鼻咽喉科・頭頸部外科の協力のもとに嚥下機能改善手術を積極的に行っている。術後の整容性、機能性などQOL向上のため、各種皮弁を応用した即時再建を基本とし、前腕皮弁、腹直筋皮弁、腓骨皮弁、肩甲骨皮弁、大胸筋皮弁、広背筋皮弁などを欠損部に応じて選択している。横尾教授の前任地の神戸大学口腔外科での5年累積生存率は手術例でStage I~IIが96.3%、 III~IVが80.0%であり、全症例ではI~IIが93.0%、 III~IVが72.4%と極めて高く、群馬大学においても今後この生存率に近づいていくものと考えている。口腔悪性黒色腫の治療では神戸大学口腔外科は分類法、治療法とも全国のパイオニア的存在で、現在群馬大学口腔外科でも同様の治療法を取り入れている。癌告知に関しては、患者個々の意識や考え方に十分配慮し、「知る権利」とともに「知らされない権利」も尊重した告知を行っている ★顎変形症=「侵襲の少ない手術法の選択」を目標としているため術前矯正の比重が大きく、上下顎同時手術などの複合手術の割合は少ない。必要に応じて骨延長術も取り入れている。下顎の手術はCT画像、3次元実態モデルを作成して術前検討を行い、下顎枝矢状分割術あるいは垂直骨切り術かを決定している。このため顎変形症手術の最大の偶発症である術後の知覚神経麻痺の発生頻度は低い。顎間固定期間は下顎枝矢状分割術では1週間、垂直骨切り術では2週間を原則としている。輸血はまず必要ないが、安全のため自己血輸血を準備し対応している ★唇顎口蓋裂=出生直後から装着するホッツ床により哺乳障害を改善し、上顎を良好な形態に誘導することを基本としており、矯正歯科医との協力のもと、年間約10例の顎裂部骨移植を施行している ★口腔インプラント=高度先進医療として認可され、年間手術件数は約40例。埋入に伴うサイナスリフトやベニヤグラフト、歯槽骨延長などの手術症例も増加している。顎義歯との併用も多い ★顎関節症=年間約250例の患者に対して、日本顎関節学会の診断基準・症型分類に基づいてスプリント療法や薬物療法、運動療法を主体とした保存療法を中心に、症例によってはパンピングマニピュレーションも実施している ★顎口腔外傷=多くは入院下で吸収性ミニプレートによる観血的整復手術を実施し、早期からの食事摂取を可能にしている ★口腔ケア=ICUでの口腔ケア回診による周術期口腔ケアや緩和ケアへの参加など、多くの場面で効果を挙げている。 |
医療設備 |
CT、MRI、核医学検査装置、手術用顕微鏡など口腔外科臨床に必要なほとんどすべての医療設備が完備されている。特に悪性腫瘍特異性のあるFMT-PETは世界で群馬大学病院のみが稼働している。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
皮膚科
分野 |
皮膚科 |
|---|---|
特色 |
当科は皮膚固有の疾患ばかりでなく、膠原病をはじめとする多数の専門外来を設け、本邦皮膚科最多のベッド数を有する。地域の皮膚メディカルセンターとして幅広く、かつ高いレベルのニーズに対応している。また、各種難治性皮膚疾患に対する基礎研究も盛んであり、常にその成果を臨床の場に還元する姿勢をとっている。詳しくはホームページ参照。 |
症例数 |
年間外来患者数は初診1,650人、再診28,000人、1日平均130人。年間入院患者数は420人。年間平均ベッド稼働率は約9割。入院患者の約4割は膠原病、約3割は皮膚外科(腫瘍、潰瘍など)、残る3割が一般皮膚疾患。膠原病の占める割合が多く、それが当科の特徴である。一方、外来診療システムは、初診は原則として講師以上が担当し、その後は専門外来にて外来主治医が一貫して担当する。専門外来担当医は、関係学会出席や研究を責務とすることで、より高度な医療の提供に努めている。病棟では、入院患者1人に対して主治医の他、経験を積んだ複数の医師がグループ制で担当する。基礎研究は、結合織代謝学、細胞生物学、アレルギー学、光生物学、免疫学を専門とするグループがそれぞれ行う。また、膠原病、アトピー性皮膚炎、皮膚腫瘍、尋常性乾癬に対する臨床研究も盛んである ★膠原病総合外来=複数の膠原病を有する患者が対象 ★強皮症外来=20年以上にわたり200人前後の全身性強皮症患者が通院している。初診時の精査により、患者の重症度や病勢をできる限り把握する。内科医との連携のもと、これまでの経験と最新の情報収集により、個々の患者に対して適切でよりよい治療を提供することに努めている ★エリテマトーデス外来=全身性エリテマトーデスに対しては、短期入院によるパルス療法などを取り入れ、効果的で患者の日常生活やQOLにも十分配慮した治療を行っている。また、皮膚限局型エリテマトーデスの治療にも力を入れており、副作用の少ない治療や、新たな病型を提唱した実績を持つ ★皮膚筋炎外来=小児から高齢者まで、通院患者の年齢分布は広く、患者それぞれに合わせた、有効で副作用の少ないオーダーメイドの治療を行っている ★シェーグレン外来=乾燥症状のみならず、全身症状に対する治療および内臓合併症の早期発見と治療に努めている ★血管炎外来=血管炎以外にベーチェット病、サルコイドーシスの治療を行っている ★皮膚形成外来=ホクロ、アザ、腫瘍、やけど、傷跡などに対して、正確な診断に基づいて、手術はもちろん、薬物療法も含めた各患者に最も適した治療を選択して行っている ★レーザー外来=ダイレーザーを使用し、単純性血管腫、苺状血管腫や毛細血管拡張症に対して治療を行っている ★腫瘍外来=当科では入院および外来において皮膚腫瘍の手術を行っている。当外来ではこれらの腫瘍切除後の患者の定期的な経過観察を行い、悪性腫瘍患者では再発や転移の有無に細心の注意を払っている ★アトピー外来=アレルギーとドライスキンの両面から、患者の症状にあわせたオーソドックスな治療とスキンケア指導を行っている ★じんま疹外来=治療はもとより、原因検索も積極的に行っている ★水疱症外来=早期より必要かつ十分な治療を行い、良好な治療成績を収めている ★乾癬外来=治療決定はあくまで患者の立場を考慮し、患者との対話の中からオーダーメイドの治療を選択するよう心掛けている。新たな治療法の研究開発も行っており、その一部は優れた効果をあげている ★脱毛症外来=症状に応じて、患者の納得する治療を心がけている。 |
医療設備 |
スーパーパルス炭酸ガスレーザー、色素レーザー、中・長波紫長外線発生装置、モノクロメーター、サーモグラフィー、ビデオマイクロスコープ、フローサイトメトリーなど。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
第1内科(内分泌糖尿病内科)
分野 |
糖尿病内分泌内科 |
|---|---|
特色 |
群馬県における内分泌・糖尿病疾患診療の中心的存在として、甲状腺、糖尿病や高脂血症等の各種内分泌・代謝疾患の診断・治療を行っている。内分泌・糖尿病代謝疾患の遺伝子診断とともに最新の専門的治療を行っている。 |
症例数 |
★内分泌疾患=クッシング病、末端肥大症、プロラクチン産生腫瘍をはじめとする各下垂体疾患、バセドウ病や橋本病を中心とした甲状腺疾患、副甲状腺疾患、クッシング症候群、原発性アルドステロン症等の副腎疾患、性腺機能低下症等の内分泌疾患症例を広く診療している。内分泌疾患の遺伝子診断を積極的に行うとともに、外来・入院診療を通じて最適な治療法を選択している。外科治療必要例に関しては、当院の外科系各診療科と密接な連携をとっている ★糖尿病・代謝疾患=糖尿病、肥満を中心とした代謝疾患の診療を行っている。代謝疾患の遺伝子診断も行い、糖尿病診療では糖尿病患者の会「あかぎ会」を中心とした外来における糖尿病教育や、2週間の教育入院など、各症例の病態に即した治療を行っている。糖尿病合併症については、網膜症は当院眼科に紹介し、神経障害や中等症までの腎症は当外来にて適切な診療を行い、重症な腎症に対し腎臓内科や泌尿器科と密接な連携をとり対応している。高度肥満症に対しては超低カロリー療法を入院管理下にて行い、良好な成績を得ている。 |
医療設備 |
診療科独自のものとして超音波診断装置を有し、病院全体の設備としてシンチグラフィー、CT、MRI、DSA等の診断装置を有する。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
血液内科
分野 |
血液内科 |
|---|---|
特色 |
白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの造血器腫瘍、再生不良性貧血、溶血性貧血、血小板減少性紫斑病などの特発性造血障害、凝固異常症、HIV感染症など広い範囲の診療を行っている。全国規模の臨床試験に積極的に参加し、細胞培養、電顕、遺伝子診断等を駆使することにより、質の高い診療を提供している。また、県内の関連病院とネットワークを形成し、それぞれの病院に特定の疾患を集め特徴を出すとともに、診療の効率化を図っており、群馬県の血液疾患診療の中心的役割を担っている。 |
症例数 |
血液専門外来の年間受診者数約800~900人、凝固専門外来受診者数100人。造血幹細胞移植症例数は県内関連施設を合わせて年間50~60例 ★急性白血病はJALSGの臨床試験に参加している。前骨髄性白血病(M3)でレチノイン酸を用いた分化誘導療法を行う以外は多剤併用療法を施行しており、完全寛解率80%に達する ★悪性リンパ腫はJCOGに参加している。B細胞性リンパ腫では原則としてリツキサン併用化学療法を行い、治療成績の向上がみられている。再発例、および初発例でも予後不良が予想される症例に対しては造血幹細胞移植を積極的に行っている。また、低悪性度B細胞リンパ腫再発例に対しては、新規薬剤ゼバリンによる治療も行っている ★多発性骨髄腫も初診時に予後因子に基づき層別化し、予後良好群に対しては標準的なMP療法、予後不良群に対しては多剤併用療法、造血幹細胞移植を行っている ★特発性造血障害については、厚労省特定疾患調査研究班、難病治療財団等に参加し、そのプロトコールに沿った治療を行っている ★HIV感染症に対しては、標準的な多剤併用療法を行うと同時に、HIVウイルスのゲノム解析を行い、その変異から薬剤耐性を予想し、治療薬剤を適宜変更することを試みている。 |
医療設備 |
骨髄移植ユニット、簡易型無菌室、MRI、各種シンチグラム、CT、PET/CT、リニアック。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
神経内科
分野 |
神経内科 |
|---|---|
特色 |
神経内科領域全般を診療の対象とするが、特に老年者に多くみられる脳血管障害、認知症、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症などの神経変性疾患を得意分野としている。その他、慢性頭痛(片頭痛、筋緊張性頭痛)、神経痛、多発性硬化症、不随意運動、てんかん、末梢神経疾患、筋疾患の患者も多い。 |
症例数 |
外来は約100人/診療日程度である。入院ベッド数は15〜20床を使用している。北関東における神経内科診療の中核施設であり、かつ群馬県唯一の大学病院神経内科であるため、多くの患者と多彩な神経内科的疾患の診療にあたっている。アルツハイマー病ではアミロイドの画像化も2009年3月から行っており、正確な診断が可能となってきている。眼瞼けいれん、片側顔面けいれん、痙性斜頸に対してはボツリヌストキシン(ボトックス)の注射を行っており、良好な成績をあげている。パーキンソン病に対しては脳神経外科と密接に連携しながら、深部脳刺激も実施している。脊髄小脳変性症に対しては高頻度磁気刺激も試験的に行っている。その他、認知症、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症などに対する臨床試験(治験)に積極的に参加している。外来では脳血管障害慢性期の患者さんは多いが、今後は脳血管障害の急性の治療にも積極的に取り組んで行きたいと考えている。 |
医療設備 |
MRI、CT、ポジトロンCT、SPECT、脳波、筋電図、血漿交換装置、高頻度磁気刺激装置など。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
- 第1内科(消化器内科・光学医療診療部)
- 呼吸器・アレルギー内科(第一内科)
- 第1外科(呼吸器外科)
- 第2外科(呼吸器外科)
- 第2外科(心臓血管外科)
- 整形外科
- 産婦人科
- 小児科
- 眼科
- 耳鼻咽喉科・頭頸部外科
- 歯科口腔外科・歯科
- 皮膚科
- 第1内科(内分泌糖尿病内科)
- 血液内科
- 神経内科
- 第2外科(乳腺・内分泌外科)
第2外科(乳腺・内分泌外科)
分野 |
乳腺・内分泌外科 |
|---|---|
特色 |
乳腺、甲状腺、副腎等を扱う内分泌外科では常に先進的治療を行っている。乳癌に対する乳房温存術など、手術創が小さくしかも従来の手術法と成績の変わらないQOLを重視した手術を施行。心臓血管外科、呼吸器外科や消化器外科の協力により、気管に浸潤した甲状腺癌や血管内に浸潤した副腎癌なども体外循環を用いて安全に手術ができる体制が整っている。 |
症例数 |
2008年の手術症例は乳癌229例(巨大葉状腫瘍1例を含む)、甲状腺腫瘍64例、バセドウ病18例、原発性上皮小体機能亢進症10例、続発性上皮小体機能亢進症 10例、副腎腫瘍20例である ★乳癌では、限局した腫瘤に対して乳房温存手術を行い、手術中の病理検査で完全切除の確認を行っている。また、リンパ転移がないと考えられる症例には、センチネルリンパ節生検を行い、腋窩リンパ節の郭清を省く試みをしている。進行例に対しては、積極的に術前化学療法を行い、縮小手術を可能にするとともに、癌細胞の完全消失を目指している。HER2陽性の進行乳癌に対してハーセプチンを併用した化学療法を行い、約50%の乳房でほとんど癌が消失していることを確認している ★甲状腺、上皮小体、副腎疾患では内分泌内科と綿密に連絡を取りながら、手術術式を決定し、術後の経過観察も行っている。良性の副腎腫瘍では腹腔鏡による副腎摘出術を行い、美容面に配慮した侵襲の少ない治療を心がけている。 |
医療設備 |
マンモグラフィ(集団検診仕様基準適合機種)、高速CT、MRI、外・内照射設備、マンモトーム。 |
「医者がすすめる専門病院 山梨・栃木・群馬」(ライフ企画 2009年6月)
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
群馬大学医学部附属病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
群馬大学医学部附属病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 名医の推薦分野について
- 名医の推薦分野に掲載する情報は、ライフ企画が独自に調査、取材し、出版する書籍、「医者がすすめる専門病院」「専門医が選んだ★印ホームドクター」から転載するものです。出版時期は、それぞれの情報ごとに記載しています。全ての情報は法人としてのQLifeの見解を示すものではなく、内容を完全に保証するものではありません。
 QLife会員になると特典多数!
QLife会員になると特典多数!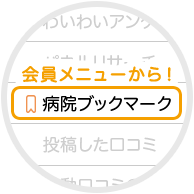

看護師丁寧な看護と処置で床ずれの発生もなし
回答者:40代 男性 勤務先:病院(200床未満)
2015年12月12日投稿
妹の知人が入院していて、よくお見舞いについて行き、看護師さんと仲良くさせていただきました。 褥瘡(じょくそう:床ずれ)の話題になった時に職場としての取り組...続きをみる