さいたま市立病院(埼玉県さいたま市緑区)が名医に推薦されている分野
専門医より推薦を受けた診療科目・診療領域
さいたま市立病院は、複数の有名専門医(※)の間で「自分や家族がかかりたい」と推薦されています。
このページでは、専門医より推薦を受けた分野(科目、領域)の特色や症例数、所属している医師について取材・調査回答書より記載しています。
※推薦、選定して頂いた有名専門医の一覧表
消化器内科
分野 |
消化器・一般内科 |
|---|---|
特色 |
東5階の消化器内科専門病床は47床であるが、他病棟入院を含め常時70人前後の入院患者の治療にあたっている。消化器内科入院総数は年間2,159人で当院入院患者総数の18.2%を占めた。東5階消化器内科専門病棟の平均在院日数は9.9日、病床利用率は97%、ベッド回転率は33.0/年であった。外来は新患者総数2,580人、再来患者総数は23,491人、1日平均外来患者数113人、紹介率は74.6%であった。また当院の緊急入院患者総数4,930人中の第1位は消化器疾患(820人、18.5%)であった。 |
症例数 |
★上部消化管、下部消化管=10年度は上部内視鏡は年間3,890例、大腸内視鏡1,910例と県内トップクラスの症例数である。消化管出血に対する緊急内視鏡数は130例で、クリッピング法・エタノール局注法・高周波凝固法を行っている。止血困難例には動脈塞栓術を行っており、手術になる症例は1%未満である。また食道静脈瘤に対する治療のEVL、EISは62件であった。05年7月から、早期胃癌に対するESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)を導入し、05年7例、06年47例、07年48例、08年81例、09年85例、10年69例と年々増加し総計337例である。最近は拡大適応病変にチャレンジし、10年11月に発表された読売新聞のランキングでは胃癌のESD数は県内5位で、当院より多い施設はすべて県内大学病院であった。最近では食道癌のESDも開始している。早期大腸癌の内視鏡治療は06年112例、07年116例、08年123例、09年121例、10年108例と県内トップで、病変は最大50mm程度のものまで切除している。現在は大腸癌でもESDを導入しており、11年は8例行った。シングルバルーン小腸内視鏡は8例、カプセル内視鏡も多数行っている。切除不能な胃癌、大腸癌に対する化学療法も積極的に行っている。潰瘍性大腸炎やクローン病に対しては、内服治療に加え顆粒球吸着療法も併用している。肝疾患B型慢性肝炎には抗ウイルス内服治療を、C型慢性肝炎にはリバビリン+ペグIFNα2b、ペグIFNα2aを中心に治療を行っている。肝癌に対してはUS・CTを定期的に行い早期発見に努め、治療としてはラジオ波治療・外科的切除術・TAE・PEIT・抗癌剤内服治療を行っている。特に最近は、転移性を含めた肝癌に対するラジオ波治療数が増加している ★胆膵疾患=腹部超音波検査は7,200件/年で、原発性肝癌、転移性肝癌に対しソナゾイド造影超音波を70件/年行っている ★ERCPは年間740例で、その91%は治療内視鏡である。EST(乳頭切開)、EBDBD(胆管バルーン拡張)は324例、胆管・膵管ステント(EBD、EPS)、胆管・胆嚢ドレナージ(ENBD 、ENGBD、ERGBD)、膵管・膵嚢胞ドレナージ(ENPD、ENCD)を多数行っている。緊急ERCP例は95例と月8例のペースであった。膵石症はこの20年間に400例治療し、本邦1位、世界3位の症例数で、独自に開発した内視鏡的膵管バルーン拡張術(EPDBD)とESWLを併用し、排石率78%、除痛率97%と良好な成績で、毎年欧米の学会で発表し高い評価を得ている。11年度にはアメリカ消化器内視鏡学会(シカゴ)、ヨーロッパ消化器病学会(ストックホルム)で発表し大きな関心を呼んだ。胆石症で適応のあるケースには外来でESWL治療を行っている。20年間に930例の治療を行い排石率80%である。PTCD、PTGBDは年間130例である。切除不能膵癌・胆嚢・胆道癌に対する化学療法も外来で行っている ★カンファレンス=毎週月曜日には外科との合同カンファレンスと消化器内科入院患者全員の検討会を行っている。また金曜日には早朝の英文抄読会を行っている。また地域の医師会とも積極的に合同症例検討会を行っている ★学会活動=この3年間で参加発表した学会は、埼玉県医学会総会、埼玉県内視鏡学会、日本臨床内科医学会、日本内科学会、日本胆道学会、日本膵臓学会、日本肝臓学会、日本消化器内視鏡学会、日本超音波医学会、日本消化器病学会、日中肝胆膵学会、日韓肝胆膵学会、アジア・太平洋消化器内視鏡学会、アメリカ肝臓学会、アメリカ消化器内視鏡学会、ヨーロッパ消化器内視鏡学会、世界膵臓学会、世界消化器病学会で講演・ポスターで参加した。また日本消化器内視鏡学会、日本消化器病学会の教育講演や教育セミナー講演を担当した。また11年度の消化器関連雑誌投稿は3編であった。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 埼玉県」(ライフ企画 2012年11月)
小児科・新生児内科
分野 |
小児医療 |
|---|---|
特色 |
★周産期母子医療センター(NICU 9床、GCU 21床)の併設、小児外科スタッフ(小児外科専門医3人)の充実により、胎児期から“児”の健やかな成育を支援する体制が整っている。地域小児医療機関との密接な連携、アレルギー疾患や内分泌疾患(低身長、肥満など)など市民のニーズに応える専門外来の設置、小児救急医療への参加により地域小児医療の中核を担っている ★日本小児科学会専門医研修施設、日本周産期・新生児医学会新生児研修施設、日本アレルギー学会認定準教育施設である。国内外学会への積極的参加、論文執筆等のmimimum requirementの達成も目標の一つである ★カンファレンスも積極的に開催しており、小児科・産科・小児外科合同カンファレンス、地域小児科医参加の症例検討会等を定期的に行っている。一般市民を対象にした“さいたま子ども健康フォーラム”を毎年開催している。育児支援の一環として成長・発達・事故防止等に関連した内容の公演を行い、質疑応答も活発である。 |
症例数 |
外来患者数は1日平均約100人、年間入院患者数は約1,400人(一般小児1,100人、新生児300人)で約半数は紹介患者である ★一般小児入院患者=約半数は感染症(肺炎、気管支炎、胃腸炎、髄膜炎等)であるが、そのほか神経疾患(けいれんなど)、代謝内分泌疾患(負荷試験含む)、アレルギー疾患(気管支喘息・アトピー性皮膚炎・食物アレルギー)、循環器疾患、血液疾患、腎臓疾患、精神保健疾患など各専門分野を網羅している ★新生児入院患者=多くは低出生体重児であり、極低出生体重児は年間約50例で、その約1/3は超低出生体重児である。NICUには手術室が併設されており、横隔膜ヘルニア等の移動が困難な症例の手術を行っている。外科的疾患症例は年間約10例 ★内分泌代謝=年間外来患者数約1,200人。低身長(成長ホルモン治療)、肥満、糖尿病(持続インスリン皮下注療法(CSII)を積極的に導入)、甲状腺疾患、副腎疾患、思春期早発症、性腺機能不全(ミクロペニス、生理不順)、先天性代謝異常、夜尿症などの診断治療、遺伝相談(臨床遺伝専門医・指導医が対応) ★アレルギー疾患=年間外来患者数約500人。気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、花粉症など。食物負荷試験を積極的に行い、症例に応じて経口免疫療法も実施している ★神経=けいれん性疾患、発達遅滞等の診断治療(月2回非常勤医師による専門外来あり) ★血液=貧血、血小板減少等の診断治療(月2回非常勤医師による専門外来あり) ★心臓血管=川崎病、先天性心疾患、不整脈等の診断治療(毎週非常勤医師による専門外来あり) ★新生児=未熟児あるいは新生児期特有の基礎疾患を有した児の成育支援 ★小児外科・小児放射線診断=スタッフが充実しており、外科的疾患(虫垂炎、鼠径ヘルニア、停留精巣、鎖肛、先天性消化管狭窄・閉鎖、ヒルシュスプルング病、先天性横隔膜ヘルニア、腸重積、膀胱尿管逆流等)、小児固形腫瘍、潰瘍性大腸炎、クローン病の診断治療も迅速に対応している ★精神保健=摂食障害、不登校、学習障害、チック等の心身症の診断治療。 |
医療設備 |
MRI、CT、超音波検査(心臓:小児循環器専門医、腹部:検査技師)、脳波、聴性脳幹反応、リニアック、ガンマカメラ、心臓カテーテル検査(心血管バイプレーンX線システム)、発達検査、心理テスト。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 △
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 埼玉県」(ライフ企画 2012年11月)
小児外科
分野 |
小児外科 |
|---|---|
特色 |
極低出生体重児から15歳までの小児外科疾患全般について治療している。新生児は周産期センター、乳児以上は小児病棟(小児科と共有)で治療している。新生児を含む一般消化器外科、呼吸器外科、救急疾患を扱い、ほぼすべての小児外科的疾患を、原則的に24時間対応で治療している。小児科、成人分野とも協力体制をとり、キャリーオーバー患者の相談にものっている。また、「排便外来」などで、排便異常、高度慢性便秘治療にあたっている。なお、思春期女児のために、要望があれば女性医のみでの診察・手術対応も可能である。 |
症例数 |
年間外来累計数は延べ5,600~5,800人前後で、うち新患者数700~800人。年間入院症例数は500例前後。年間手術件数は360~400例で、うち腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術約150例、精巣固定術(腹腔鏡下補助含む)約50例、臍ヘルニア手術約40例、腹腔鏡下虫垂炎手術約40例。その他、肥厚性幽門狭窄症、食道閉鎖、腸閉鎖、直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病、総胆管拡張症、胆道閉鎖症、横隔膜ヘルニア、臍帯ヘルニア、異物誤飲・誤嚥、包茎、正中頸嚢腫などの頸部疾患、漏斗胸、肺嚢胞症、腫瘍などの手術を行っている。 |
医療設備 |
周産期母子センター(NICU内手術室あり、HFO、NOなど含む新生児集中治療可能)、内視鏡センター、MRI・32列2管球CTなどの各種画像装置、鏡視下手術、消化管内圧測定、24時間pHモニターなど。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 △
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 埼玉県」(ライフ企画 2012年11月)
内科
分野 |
リウマチ・膠原病内科 |
|---|---|
特色 |
関節リウマチをはじめとするあらゆるリウマチ・膠原病疾患に対応している。早期発見、早期治療に力を入れており、疑い例についても積極的に診療を受け入れている。リウマチ・膠原病疾患は全身病であるという認識から、全身管理を心がけており、また総合病院で他診療科が充実しているという利点を生かし、精神科領域を除くほぼすべての病態に対応が可能である。地域の大学病院・他の基幹病院のみならず都内の大学病院とも交流があり、常に最新の治療を取り入れるよう心がけている。 |
症例数 |
年間患者数約600例、うち約半数が関節リウマチ、残りの半数が他の膠原病である ★関節リウマチについては、発症早期段階での積極的な治療による寛解導入および関節変形の防止に重点を置いている。生物学的製剤導入例は110例。関節リウマチ患者の約8割で寛解または低疾患活動性を達成、維持している。また、入院施設をもつ総合病院の利点を生かし、最新治療に伴う副作用、ことに感染症対策にも力を入れている ★他の膠原病患者については、生命予後を重視した各疾患に応じた治療を取り入れており、すでに10年以上良好な状態を維持し、当院でフォローアップを継続している患者が多数出ている。膠原病の合併症で最近問題となっている肺動脈性肺高血圧症に対しても、循環器内科とタイアップして力を入れており、フローラン導入を除いて当院での対応が可能となっている。 |
医療設備 |
地域の核となる総合病院として必要な設備はすべて整っている。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 埼玉県」(ライフ企画 2012年11月)
神経内科
分野 |
神経内科 |
|---|---|
特色 |
神経内科領域の疾患に幅広く対応しているが、救急患者が多い当病院の特性として、神経内科領域の救急疾患が主体となっている。とくに急性期脳梗塞に関しては市内、県下ではトップクラスの診療実績を有している。なお、日本神経学会准教育施設、日本脳卒中学会認定研修教育病院、日本内科学会認定制度教育病院にそれぞれ認定されている。 |
症例数 |
内科の一部門である神経内科として専門性を維持する一方で、内科の各専門分野や脳神経外科をはじめとした他科との協力・連携を図って診療にあたっている。また、浦和医師会などの市内各診療所などとの病診連携も重視して診療を行っている ★11年の年間外来患者総数は10,828人で、うち新規外来患者は1,596人である。年間の新入院患者数は552人で、その過半数が急性期脳梗塞である。公表されているDPC統計データ(10年7月~11年3月)では、埼玉県下で埼玉医大国際医療センターに次いで2位、全国でも150位の脳梗塞の診療実績を誇っている ★脳梗塞超急性期の血栓溶解療法については、オンコール体制で24時間対応しており、11年は年間13人に実施した。また、脳血管内治療や内頚動脈内膜剥離術も必要な場合には脳神経外科に依頼している。脳血管障害急性期の症例は、急性期からのリハビリテーション開始を積極的に行っている。さらに、回復期リハビリが必要な場合は、地域連携パスを積極的に利用してリハビリテーション専門病院への転院を勧めている ★その他にけいれん性疾患、脳炎・髄膜炎、ギラン・バレー症候群、重症筋無力症、多発性硬化症・脊髄炎、パーキンソン病および類縁疾患、筋萎縮性側索硬化症などの疾患に幅広く対応している。免疫グロブリン療法や各種血液浄化療法などは随時施行可能である。また、ボトックス療法(顔面攣縮、眼瞼攣縮のみ)も外来にて行っている。 |
医療設備 |
MRI(3テスラ・1.5テスラ)、CT(64列マルチスライスCTを含む)、RI、血管超音波検査、末梢神経伝導速度検査、筋電図検査、脳波検査など。 |
- セカンドオピニオン受入 △
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ○
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 埼玉県」(ライフ企画 2012年11月)
放射線科
分野 |
放射線科 |
|---|---|
特色 |
放射線診断(画像診断)、核医学、放射線治療の3部門で構成。院内各科との連携を密に、これらの診療に当たっているが、病診連携の一環として地域開業医からのCT、MR、RIなどの検査依頼に対応している。また、他院からの放射線治療の依頼にも対応。 |
症例数 |
★年間(11年度)の検査件数は、CT:17,602件、MR:5,372件、RI:574件、血管造影:114件(うちIVR:74件)である。血管造影では診断を目的としたものよりも、治療を目的としたIVRが主流となりつつある。特に肝癌に対する塞栓術の施行、消化管出血や子宮出血に対する塞栓術、肝右葉切除術前の門脈塞栓術、さらに肝転移に対するリザーバー留置などで成果をあげている。また院外からのCT、MR、US等の検査依頼にも対応している。常勤医による報告書作成率は80%を超え、画像診断管理加算2を得ている。なお、いずれの検査も予約待ち1週間以内を目標としている。MRについては需要に追いつけない状況が続いているが、緊急度の高い症例については数日以内に実施できる体制を整えている ★放射線治療患者は年間159人(うち新患128人)。リニアックによるX線、電子線照射を実施している。化学療法の併用や術前・術後照射など、各科と連携して集学的治療の一環を担っている。院内各科からの依頼患者が主だが、院外からの依頼にも対応している。 |
医療設備 |
CT 2台(4列と64列、4列については13年度更新予定)、MR 2台(1.5テスラと3テスラ)、血管造影装置2台、RI 2台(12年度SPECT-CTに更新予定)、リニアック、治療位置決め装置、治療計画装置(13年度IMRT対応にversion up予定)など。 |
- セカンドオピニオン受入 ○
- 初診予約 ○
- 主治医指名 ×
- 執刀医指名 /
○=可能 △=条件付きで可 ×=不可 /=未回答
「医者がすすめる専門病院 埼玉県」(ライフ企画 2012年11月)
QLifeでは次の治験にご協力いただける方を募集しています
治験参加メリット:専門医による詳しい検査、検査費用の負担、負担軽減費など
インフォメーション
さいたま市立病院を見ている方は、他にこんな病院を見ています
さいたま市立病院の近くにある病院
おすすめの記事
- 医療機関の情報について
-
掲載している医療機関の情報は、株式会社ウェルネスより提供を受けて掲載しています。この情報は、保険医療機関・保険薬局の指定一覧(地方厚生局作成)をもとに、各医療機関からの提供された情報や、QLifeおよび株式会社ウェルネスが独自に収集した情報をふまえて作成されています。
正確な情報提供に努めていますが、診療時間や診療内容、予約の要否などが変更されていることがありますので、受診前に直接医療機関へ確認してください。
- 名医の推薦分野について
- 名医の推薦分野に掲載する情報は、ライフ企画が独自に調査、取材し、出版する書籍、「医者がすすめる専門病院」「専門医が選んだ★印ホームドクター」から転載するものです。出版時期は、それぞれの情報ごとに記載しています。全ての情報は法人としてのQLifeの見解を示すものではなく、内容を完全に保証するものではありません。
 QLife会員になると特典多数!
QLife会員になると特典多数!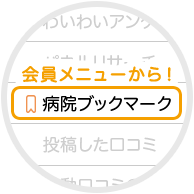

診療科目:心臓血管外科
50代以上女性 2018年04月11日投稿
息切れの症状は、前からあったのですが、以前行ってい他病院では3回目の手術という事もあり、リスクが大きいと、手術はやらないと言われ続けていた為、個人病院から紹介で、日赤に来…続きをみる